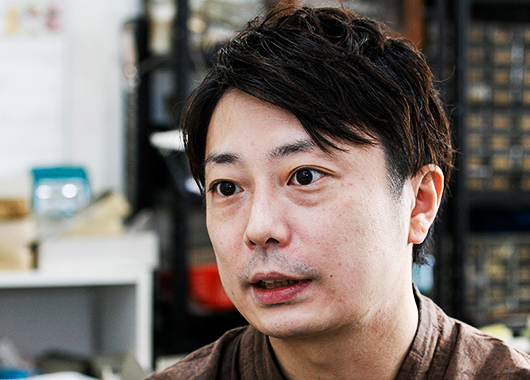
気品あるれる京象嵌を生み出す職人技
漆黒に浮かび上がる、金銀で彩られた四季の風物。気品あふれる京象嵌を生み出しているのが、中嶋象嵌である。
象嵌は15工程を経て完成するが、最も難しく重要なのが最初の『布目切り』だ。土台である地金にタガネを当て、槌で叩きながら微妙に移動させて細かい溝を縦横に彫っていく。その間隔は、なんと1mmに8~7本。肉眼では見えないので、指先のカンだけで彫るのだ。ルーペで見ると微細な剣山のようになっており、この凹凸に模様を打ちこんで定着させる。溝が浅かったり布目の間隔が均一でないと模様がはがれやすくなるため、根気よく丁寧に施さねばならない。「布目切りを習得するには最低5年、確実にできるようになるには10年はかかります」と中嶋氏は言う。
平面でも難しいのに、曲面や球体に彫るとなればいっそう高度なテクニックを要するため、ベテラン職人の腕の見せ所である。それだけに布目切りを機械化した工房もあるそうだが、中嶋象嵌ではすべて手作業で行っている。
布目切りを終えた地金には、金や銀の模様をあてがい、上から槌で叩いて布目に嵌めこむ『入嵌(にゅうがん)』を施す。この模様を抜く型もオリジナルで、工房のセンスが問われる大切な道具である。また、入嵌に下絵はなく、アタリだけでバランスを考えながら打ちこんでいく。やり直しがきかないため、やはり職人技が発揮される工程だ。その後、布目を消すための腐食や錆出し、仕上げの漆焼き、模様を研き出すなどの工程を経て、ようやく完成する。






