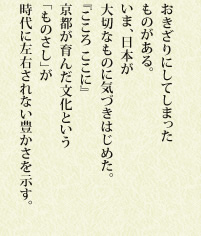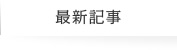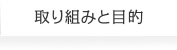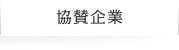リレーメッセージアーカイブ
![]()

■知恵と工夫のDNA
平安時代から都市であり続けた京都には、何度も危機があったはず。しかしその都度、知恵と工夫で不死鳥のように甦(よみがえ)り歴史を刻んできた。近いところでは明治時代、疏水事業に代表される近代的都市基盤整備を行い、積極的に外国の技術を導入した開明的な企業人の努力などによって、東京遷都の大打撃を乗り切った。また、戦後の復興期には、伝統技術を先端技術に昇華させたベンチャー企業が次々に生まれ、「京都銘柄」の上場が相次ぎ、京都発の世界企業が誕生していった。歴史は革新あってこそであり、京都の濃密で重層的な都市の力がそれを支えてきた。
今日に至るまで、新しい技術やビジネスモデルの創出は京都の強みとなり、独自性の強い企業が数多く存在している。京都の企業は、海外での圧倒的なブランド力や都市そのものの魅力によって、容易に本社を移したりはしない。京都の文化や芸術が変らず命脈を保てるのも、地元企業の力によるところが大きい。
その京都も近年、事業所数や生産年齢人口の減少が続いている。混沌(こんとん)としたこの時代にこそ、知恵と工夫のDNAを呼び覚ますことが大切だ。
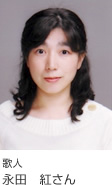
■言葉をのこす
昨年8月、64歳で母が亡くなった。乳がんだった。
母は河野裕子(かわのゆうこ)という歌人で、入院中も、在宅看護に移ってからも、原稿を書き、新聞歌壇の選歌を続けた。ベッドの上で、仰向(あおむ)けのまま投稿歌のハガキを繰っていた姿を思い出す。先日、母のマットレスを干そうと持ち上げてみると、隙間に何枚か投稿ハガキが落ちているのが見つかって、ああ、と思った。
作った歌は、ベッドの上で手帳に書きつけていたが、鉛筆を持つ力がなくなると、家族が口述筆記をした。亡くなる前日、父が聞き取った、
手をのべてあなたとあなたに触れたきに息が足りないこの世の息が
河野裕子『蟬声(せんせい)』
が母の最後の歌になった。
死の直前まで、母に歌を作らせた力は何であったのだろう。傍(そば)で見ていると、それは無理をしているというよりも、母にとってごく自然なことのように感じられた。歌の数々は、今も母の存在を身近に留めてくれている。お守りのように。日々にまぎれて多くの言葉は流れていってしまいがちだけれど、「言葉をのこす」ということ、「言葉はのこる」ということを思う。

■満月の夜に思うこと
子供のころ、姉と二人、よく母に手を引かれて仏教の講話の会や座禅の会に行った。大人に混じり高僧のお話を聞いていて、「今は幼くてわけがわからなくても、こういうものは毛穴から入るものなのよ」と言われた。また家が近所だったカトリックの聖イグナチオ教会の日曜学校にも通わされた。当時、名司祭の誉れ高いホイヴェルス神父さまが講話の後、「私のような者のお話を聞いて頂いて有難う」と心からお礼を言われ、なんて謙虚な方なのだろうと母が感心していた。
「いつも謙虚な心を忘れずに」「事を図るは人に在り、事を成すは天に在り」など折に触れ言われて育てられた。今この年代になって果たして母の言葉どおりに生きてこられたかと問うと、甚だ心もとない。その母も、昨秋、満月の日に旅立ってしまった。
母を失った今、日本人の忘れもの、すなわち私自身がひたすら前ばかりを見て走り続けてきた結果、見失ってしまった大切なものを静かに考えてみたいと思っている。そして京都には、やはり宗教的なものの見方をもう一度日本人の心に、ということを期待したい。

■時雨(しぐれ)
東京から京都に移り住んで七年になる。はじめての年、驚いたのは冬の雨の多さである。特に秋の終わりから冬の初めにかけて、気まぐれな空は、晴れたまま雨を降らせたり、さっと曇ってひとしきり降ったかと思うと、また何事もなかったかのように晴れ渡ったり。「時雨」という美しい名で呼ばれる雨だ。初冬に降る通り雨といった「時雨」の辞書的な意味を知ってはいても、東京でそれを経験することはほとんどなかった。
古典和歌には「色々に染むる時雨にもみぢ葉は争ひかねて散り果てにけり」のように、時雨が木々の葉を染めるという表現が頻出する。時雨が降るたびに紅葉の色が深まっていくことを、私は京都ではじめて実感したのである。時雨によって木の葉が色づくという和歌の類型は、まさに京都でこそはぐくまれたのだった。
室町時代末の流行歌謡・小歌(こうた)の中には、屋根に降りかかる時雨の音に孤独を慰めようとする、こんな一首もある。
せめて時雨れよかし
ひとり板屋のさびしきに
こうした、身近な自然に寄り添う繊細な感性を大切にしたいと思う。