やなぎみわさんがホストを務める「日本人の忘れもの知恵会議」の連続対談4回目は、蒔絵(まきえ)師で京都産業大名誉教授の下出祐太郎さんを迎え、下出さんの冒頭解説に続いて「伝統と産業の未来」をテーマに語り合った。コーディネーターは京都新聞総合研究所特別編集委員の内田孝が務めた。
対談シリーズ
Conversation series
未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2022年第4回】
(2022年7月/京都産業大)
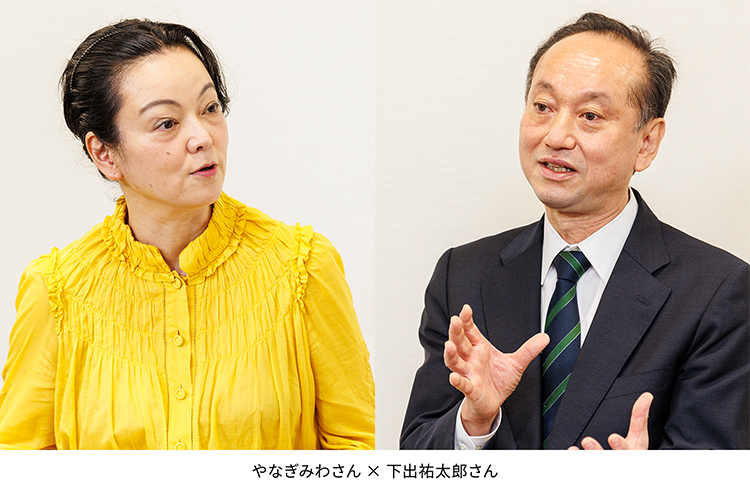
■対談
伝統と産業の未来
オリジン失わず前に進もう
やなぎみわ氏(美術作家/舞台演出家)
高台寺蒔絵復元で技術継承
下出祐太郎氏(下出蒔絵司所三代目/京都産業大名誉教授)
冒頭解説「蒔絵の歴史」
安土桃山期、地震・戦乱で仕上げ急ぐ?
下出◉蒔絵は、器などの表面に漆で絵を描き、漆が固まらないうちに金属粉を蒔きつけて模様を施す技法です。平安時代から受け継がれる蒔絵技術の原型は、正倉院にある「金銀鈿荘唐大刀(きんぎんでんかざりのからたち)」の鞘部分の技法にあるとされています。ただ、北海道の約9千年前の遺跡から繊維に漆を染み込ませた副葬品が出土しており、漆製品としては世界最古ですので、蒔絵の歴史もまだまだ広がる可能性があります。学校で学ぶ歴史は文献学が中心ですが、物的資料と合致しないこともありますので、そこは柔軟に考えて学ぶことが重要です。
京都の東山山麓にある高台寺は、豊臣秀吉の正室・ねね(北政所)が秀吉の菩提を弔うために建立し、秀吉やねねの座像を安置するお堂「霊屋(おたまや)」があります。霊屋内部の座像を納める厨子(ずし)扉などに施された蒔絵は「高台寺蒔絵」と呼ばれ、安土桃山時代を代表する様式です。
2002年、詳細な調査結果を基に、現代の技術や素材も活用して厨子扉計4点を復元制作する機会を得ました。厨子扉は、秀吉が築いた伏見城(京都市伏見区)の遺構と伝えられています。蒔絵には期待に反し、輪郭からはみ出た線描、途中で描くのを止めた箇所が散見され、初めて厨子扉を見た時に残念に思ったことがあります。蒔絵師として名高い幸阿弥家の職人たちなのに「なぜこんな粗っぽい仕事をしたのか」。謎を解き明かそうと制作に臨みました。
調査の結果、現代と異なる金粉の使用、金粉を蒔いた後に漆が乾かないうちに針状のもので引っ掻くように金をはがし、下地の部分で細い線を表現する「針描(はりがき)」の採用も分かりました。「作業時間短縮を狙ったのではないか」と考えています。復元的制作には、私の工房の職人8人がかりで約2カ月かかりました。安土桃山時代なら、温度や湿度を一定に保つ設備などもありませんので、1年以上の時間を要したでしょう。雑な仕事をしている部分は、何らかの状況変化があって、急いで仕上げなければならなかったのではないかと考えています。戦乱の激化、1596(文禄5)年に発生して伏見城が大きな被害を受けた伏見大地震の影響があったかもしれません。戦国武将が身命を賭して覇権を争っていたように、蒔絵師たちも秀吉の命を受け、命を懸けて取り組んだのではないでしょうか。
やなぎ◉祖父の代から続く蒔絵工房の家に生まれ、子どものころから身近に蒔絵があったと思いますが、どのような心持ちで漆芸の道に進もうと決めたのでしょうか。
下出◉小児ぜんそくを患い、医師からは「小学校卒業までもたない」といわれていました。退院しても、夜になると「病院に帰ろう」と言うくらい病院漬けの子供だったそうです。幼少期の記憶はほとんどないのですが、当時は元気になったら蒔絵ができるという希望を持たせられて過ごしていたのではないでしょうか。祖父や父からは「自分の好きなことをすればいい」と言われていましたので、大学は文学部に進み、詩の創作に打ち込みました。
大学卒業後、家業に入りますが、明けても暮れても漆を練るなどの下仕事ばかり。初めて「自分の人生はこれでいいのか」と疑問を持ちました。転機となったのは、漆芸家・東端真筰先生(1913~78年)との出会いです。大画面のパネル作品などを手掛け、世界で勝負している姿に憧れ、すぐに弟子入りしました。東端先生のもとでも変わらず下仕事でしたが、「いつか東端先生と同じような活躍をしたい」と思うだけで、毎日わくわくするような気持ちでした。
やなぎ◉私は京都市立芸術大で染織を専攻し、型友禅の技法で着物や屏風などを制作していました。昼夜を問わず大学の工房で作品づくりに取り組みました。今でも工房に足を踏み入れた時や、染料や糊、蝋の匂いを感じると、不思議と感情が高ぶります。学生時代に京友禅の会社で働かせてもらった経験もありますし、工芸が大好きでしたが、4年生でドロップアウトして、工芸とは異なる表現方法や素材を模索するようになりました。
下出◉工芸の領域から距離を置いたのはなぜですか。
やなぎ◉理由の一つは、他の表現との交流です。油画の制作室に行くと、彼らは最後まで作品をどうするか悩み、時に完成間際の絵を塗りつぶして、最初からやり直すこともありました。一方、工芸はまず下絵を描き、計画を立て、手順を決めて作業を進めます。考えるのは下絵が完成するまでで、それ以降はプラン通りに進めなければ作品は完成しません。素材も高価なものが多いので、無駄にしないよう気をつける必要もあります。息苦しさを感じ、最終的には実験的な作品づくりに向かいました。
ところで、下出さんは、高台寺蒔絵について、伏見城の完成に合わせた仕上げに期限があったとお考えなのですね。
下出◉そう思います。依頼主である秀吉には一晩で城を築いたという伝説もありますので、「いついつまでに仕上げなければ首を飛ばすぞ」と、職人らに発破をかけていても不思議ではありません。彼らは締め切りに何が何でも間に合わせたのでしょう。
厨子扉1枚は高さ150センチ、幅70センチほどです。蒔絵が大型の建築装飾として、高台寺蒔絵で初めて使われた可能性も指摘されています。器などであれば手に持ちながら作業を進めることができますが、厨子扉の場合は床の上に置いて、上からのしかかって作業をしなければなりません。熟練工でも、針描で菊の花を一つ描くのが精いっぱいだったのではないでしょうか。

2011年に復元的制作がなされた秀吉公厨子扉裏「源氏雲に菊楓五七桐紋散らし」。下出さんは「こちらが扉表だったのではないか」と推測する
(提供・下出蒔絵司所)
やなぎ◉芸術は時の権力者の影響を大きく受けます。武士や貴族ら、特権階級の権力を象徴するものとして美術作品や工芸品づくりは保護を受け、一流の画家や職人が制作に当たりました。蒔絵や着物などの素材は次第に豪華になり、細工や技巧も精緻になっていきました。京友禅は染めや水洗い、刺繍など10以上の工程があり、専門業者による分業制も敷かれています。京都では半製品が一定エリアに集まる専門業者の間をぐるぐる回ることで、一反の着物が出来上がるといわれています。
下出◉着物分野で分業化が進んだのは、長年工程ごとに試行錯誤や改善が繰り返され、技術やノウハウが洗練されることによって、職人の専門性が高まったからです。太古の時代からさまざまな天然素材を用いてものづくりを続けてきたことで、人間の英知は積み重なり、社会は発展してきました。高台寺蒔絵の復元で、現代の金粉を使ったり、新たに工程を追加したりしたのは、そのものづくりの営みを止めずに、将来に向けて技術を引き継いでいくためです。
やなぎ◉日本画は鉱物や貝殻などを素材にした絵の具を用い、紙や絹の画面に絵を描きます。絵の具を定着させる接着剤には動物由来の膠(にかわ)が欠かせません。京都は映画産業が盛んでしたが、写真や映画のフィルムの感光材料にも膠が使われていました。ただ、これらの自然由来の原材料は安定的に供給することが難しく、時代とともに環境保護などの観点からも確保が困難になりつつあります。
下出◉蒔絵に使う漆も国産が減り、多くを中国産に頼っているのが現状です。日本では漆の成木から樹液を1年で取り尽くしてしまいます。樹液の採取のためには、計画的な植林をして、近代産業以前の持続可能な生産サイクルを再構築する必要があります。産業革命以降、機械化によって生産性が一気に向上。為政者や特権階級によって支えられ、発展してきた工芸品も多くの人が手にすることができるようになりました。ただ、現代の産業構造は効率や利潤を最優先に考える志向が強く、天然素材を使った創作や生産には向かい風となっています。
双方には隔たりがあるように見えますが、ものづくりの出発点は同じところにあります。人間の英知をさらに豊かにするためにも、地球規模での持続可能な自然観に根差した経済システムを構築する必要があるでしょう。
やなぎ◉美術や工芸、芸能に携わる人たちは、いつの時代もバトンを次世代につなぐ使命感を持って活動しているはずです。デジタル技術の発達により、元になるデータや資本、設備があれば芸術作品も大量生産が可能になり、世界規模のビジネスとして展開できる時代に突入しました。全ての活動がその仕組みにのみ込まれてしまうと、「オリジン(原点、根本)」は失われてしまいます。進むべき道がどんなに細く、狭くなろうとも私たちは前に進まなければなりません。
■質疑
産大生◉海外ブランドの広告で、モデルが着物や帯の上を歩き、「異文化への尊敬の念に欠ける」と批判を受けました。工芸品や美術作品に対しては、起源や歴史を理解し、互いに敬う気持ちが大事なのではないかと感じます。
下出◉欧州で蒔絵について紹介する機会があったとき、「日本にはまだこんな技術が残っているのか。大事にしてください」と現地の人が声を掛けてくれました。文化や自然環境を失うと、どんな損失や影響があるのか、それぞれが考えることが大事でしょう。
産大生◉使いやすいものが安価で簡単に大量生産できる時代ですが、逆に個々の人たちの価値観や好みをデザインして、作品や商品に反映させるにはどうすればいいのでしょうか。
やなぎ◉独創的なデザイン、アート的な実用品は、昔も今も求められていると思います。
用途や既存の美など全てから自由なのがファインアートですが、工芸を手放したあと、その憧れていた自由の寄る辺のなさに悩みました。
正直、学生時代は周囲や社会のことはあまり考えていませんでした。もっと自己表現や自分の中を掘り下げて創作することにこだわっていました。一方、大学には工業デザインを学ぶ同級生らもおり、彼らは社会に有用なものや依頼主に求められるものを作り出していましたので、その姿を見ていたのは良かったと思います。
産大生◉時代が変わっていく中で、新しいものを取り入れると、古いものは失われていきます。オリジンを守らなければならないのはなぜでしょうか。
下出◉神社の例祭一つをとっても、私たちは季節の訪れや収穫のありがたさを感じ、地域の文化を守り、自然と共生することの意義も再確認できます。日本には神社を中心に、住民が自然と調和しながら豊かに暮らしていく仕組みがあります。今後、新しいものと古いものを融合させ、これまでにない価値や品質を生み出そうとしたときに、神社のような「オリジン」の存在は一層大事になってくるはずです。
やなぎ◉文化財の復元は時空をさかのぼっていく行為で、それを通して自分の立ち位置が分かると、未来に向けて新しい第一歩をどう踏み出すかも見えてくるでしょう。

◎下出祐太郎(しもで・ゆうたろう)
1955年生まれ。蒔絵師として、即位礼や大嘗祭の神祇調度蒔絵、京都迎賓館の飾り台などを手掛ける。詩人としてはH氏賞候補2回。共著に「京の美の継承」など。
◎やなぎみわ
1967年生まれ。京都市立芸術大で染織専攻。昨年末の台湾など、国内外でメッセージ性のある舞台公演を手掛ける。近年、踊り念仏で知られる一遍上人と芸能の関わりに着目。

