目・耳・鼻・舌・皮膚によって、私たちは身体の周囲を把握し、世界を実感している。全盲で「さわる」ことで世界とコンタクトしてきた文化人類学者の広瀬浩二郎さんと、五感と文化・芸能の関係を考察する編集工学者の松岡正剛さんが、オンラインで自在に語り合った。コーディネーターは京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。
対談シリーズ
Conversation series
未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2021年第5回】
(2021年9月/オンライン) ◉ 実際の掲載紙面はこちら
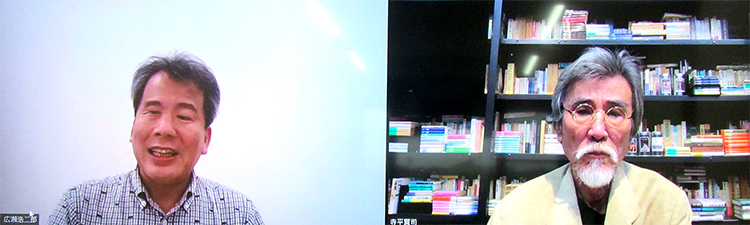
■対談
見えないものを見るために
「面影」引き出す仕組み活用を
松岡正剛氏(編集工学者)
触覚通し「世界」と関わる自信
広瀬浩二郎氏(文化人類学者)

松岡◉私は京都の悉皆(しっかい)屋に生まれました。ほとんど耳の聞こえないおばさんに、仕立てものを届けたことがありました。おばさんは読唇術でコミュニケーションを取っており、口の形などで意思伝達することに驚きました。生まれついて全盲の叔父もおり、よく一緒に百貨店や風呂屋へ行きました。あるとき、百貨店1階で叔父が「いい音が聞こえるね」と。「どんな音?」「風鈴かな」「そんな音、聞こえへんで」といったやりとりをしながら買い物を済ませ、5階に上がると、風鈴が並んでいました。
風呂屋で叔父は「小さい方の湯船に入りたい」と言ったこともあります。音の聞こえ方で、空間の広さや奥行きを把握したそうです。人の感覚機能を五感といいますが、耳は聴覚、目は視覚であるとは限らず、外界からの刺激を感覚器官や脳、身体で変換して感じ取っていたのでしょう。
広瀬◉叔父さんはすごく勘のいい視覚障害者だと思います。健常者は外界からの情報の多くを視覚から得ているといわれますが、視覚障害者は聴覚や触覚を媒介として情報を得ているのです。
風鈴の音は耳を澄ませば松岡少年にも聞こえたと思いますが、きっと叔父さんをサポートしようと、きょろきょろして視覚に意識がいっていたので聞こえなかったのでしょう。邪念だらけの今の僕にも、風鈴の音は聞こえないかもしれませんね。
松岡◉私たちの知覚は情報を「良い加減」につかまえるようになっています。ある種の恣意(しい)性を知覚が持つようになって、恣意性を突き詰めていくとバッタになったり、セミになったりと、生物の進化はその知覚の偏りを特化していく過程で起こっているとも言えます。元々、人は4本足で歩行していたのが直立2足歩行になり、草食から雑食になり、全身を覆っていた毛や牙を失いました。それによって劣化してしまった感覚もあるのでしょう。
一方で、靴の中に小さなごみが入っただけでも違和感を覚える鋭さもあります。ただ、足の裏の感覚情報すべてを受け取ると、歩くたびに刺激を感じすぎるので、適度に感じないようになっているのでしょう。
広瀬◉自分の日常生活を振り返ってみると、視覚が使えないので、入ってくる情報はおのずと限定されます。しかし、入ってくる情報が少ない分、手にした情報は能動的に処理しようとしている気がします。風呂の反響音や遠くから聞こえる風鈴の音を手掛かりとして、自分なりの「世界」を想像・創造していくのです。
「視覚障害者は記憶力がいい」とよく言われます。点字を紙に書く作業では手を動かして一点一点打っていきますし、物をさわる際も手を動かします。「世界」との関わり方が受動的ではなく、能動的にならざるを得ないわけです。情報を取得するために必然的に身体動作を伴うので、記憶としても残りやすいのだと僕は考えています。
松岡◉人は2足歩行への進化とともにしっぽを失い、感覚機能は目・鼻・口・耳と脳がある頭部に集中しました。しっぽによって風向きや接触を知覚する動物に比べ、私たちは首から下の身体や肌、手足の感覚がかなり摩滅したように感じます。進化の過程で失った感覚を取り戻すには、しっぽについて考察する「尾学(びがく)」を誰かが立ち上げる必要があるでしょう。
広瀬◉「尾学」はおもしろいですね。同じような意味で、僕は「触角」という語を使っています。かつて、人間は昆虫のような触角を持っており、全身の触角を働かせて、「世界」と関わっていた。視覚優位の近代という時代の到来により、人間は触角を失ってしまったのではないでしょうか。
視覚に障害がある人は白い杖(つえ)を持って歩いているので、3足歩行とも言えます。杖は歩行時の不自由さを補う道具ですが、発想を変えると、しっぽ・触角ともとらえることができます。3本足で歩く障害者には、2本足で歩く多数派と4足歩行をしていた太古の祖先の間を往還し、人類が失ってしまった感覚を復活させる、そんな役割もあるのではないでしょうか。


松岡◉私の父が滋賀県長浜市出身で地元に菩提(ぼだい)寺もあり、最近、近江=滋賀県に関心を寄せています。平安時代の琵琶の名手、蝉丸(せみまる/生没年不詳)を祭る関蝉丸神社が大津市逢坂にあります。琵琶を用いた音楽や語りは、南北朝時代に活躍する琵琶奏者・明石覚一(かくいち/?~1371年)らへと引き継がれ、近世に発展する三味線音楽にも大きな影響を与えています。蝉丸や覚一らは全盲です。邦楽は拍子が等間隔ではなく、独特の間があります。能の囃子(はやし)も同じで、あのような小鼓や大鼓の打ち方は世界のどこにもありません。この独特の間合いは目の見えない人たちが関与することで生み出されたのではないかというのが私の仮説です。
広瀬◉琵琶の伴奏で平家物語を語る平曲は、語りの合間に琵琶の音が入っています。琵琶の弦が揺れて空気を振るわせ、その振動が広がっていく。琵琶奏者は、振動が広がる時間や空間を身体で感じており、それが独特の間につながっているのでしょう。また、聴衆にとっても平曲の世界に入り、物語のイメージを広げていくためには、琵琶奏者の声と楽器の音を身体に取り込む時間的な余裕やゆとりが必要です。平曲を楽しんでいた中世・近世の日本人は、受動的ではなく、能動的に「世界」と関わっていたわけです。そんなかつての日本人からすると、冒頭の松岡さんの叔父さんのエピソードは、ごく当たり前のものなのかもしれませんね。
松岡◉琵琶法師と同じように、明治生まれの作曲家で、筝曲(そうきょく)家・宮城道雄(1894~1956年)の作品にも空間を意識した音の並びや響きを感じます。それは西洋音楽のオーケストレーションのように、メトロノームを基準にして五線譜上に数学的に割り振れるようなものではありません。現代作曲家の武満徹(1930~1996年)は余白や何もない空間の大切さに気付き、尺八や琵琶を取り入れた作品を残しています。
広瀬◉2021年9月から、国立民族学博物館(民博、大阪府吹田市)で特別展「ユニバーサル・ミュージアム」を開催しています。さわって体感できるアート作品を集めた展覧会です。特別展の中に、盲学校の中学生たちが制作した陶芸作品を紹介するコーナーもあります。彼らは「見る/見られる」ことをまったく意識せず、自分のさわった感覚だけを頼りに作品制作に取り組んでいます。触角、あるいはしっぽをフル活用することから生まれる「古くて新しい」アートといえるでしょう。
そんなユニークな表現手法を障害者や盲学校生徒という枠に閉じ込めてしまうのは、なんとももったいない。特別展では「タッチアート」という新しいコンセプトを打ち出し、その代表例として盲学校生徒の作品を位置付けています。作品にさわることを通して、制作者と鑑賞者が文字どおり握手する。「障害」の有無に関係なく、自由な交流や対話ができればいいなと考えています。タッチアートは、いわば現代版の平曲です。タッチアートにさわれば、「日本人の忘れもの」を取り戻すこともできるのではないかと期待しています。
松岡◉一つの刺激に対して、通常の感覚だけでなく、ほかの種類の感覚も得る「共感覚」という知覚現象があります。例えばあるものを味わうと形や色が見えたり、音が聞こえたりすることです。民博での展覧会で、触った時に何を感じたか調査をしたり、共感覚の実験をしたりしてみるのも面白いのではないでしょうか。
広瀬◉今、僕は全盲ですが、小学生のころは右目だけ少し見えていました。地域の学校に通っており、図工の授業では同級生とともに絵を描いたり、工作をしていました。悪ガキだった僕は、絵の具でいたずらばかりしており、よく先生に叱られたものです。左目が見えないので、遠近感がうまくつかめない。僕の絵は、同級生の作品とは明らかに違っていました。今なら「俺はピカソだ!」と開き直って、自作を自慢すると思いますが、当時は周囲との「違い」に戸惑い、居心地の悪さを感じていました。図工の先生が「人それぞれに見方は違う」「さまざまな表現方法があってもいい」という指導をしてくれていたら、図工は苦手な科目にならなかったかもしれません。
中学から盲学校に進学し、美術の授業では触覚を中心に作品制作するようになります。当時の僕はまだ「かっこよく見せたい」という意識が強く、タッチアートの境地には至っていませんでしたが、「さわって創る」「創ってさわる」楽しさを再認識できたのはよかったと思います。「自分は不器用ではない」「周囲と違っていてもいいんだ」。盲学校の美術の授業を通じて、僕は自らの手で「世界」と関わる自信を得ることができました。
松岡◉私は長年編集について論考を重ねてきましたが、例えば「ギトギト」というオノマトペが油っぽい状態を表すように、何かと何かをまたいだり、つないだりするエディティング・フィルターが情報には潜んでいて、単純な知覚を超えて複合的に人に作用していると私は考えています。そこで私が重要視しているのは面影です。父や母はすでに他界しましたが、今でも顔つきや姿は思い浮かびます。文学作品を読んで、映像的にイメージが膨らむのも面影です。日本では目に見えないものが、神様になったり、トトロのような森の主になったり、怪物になったりします。そういったものが失われてしまうと、きっと児童画もつまらなくなるし、アートもごくありふれたものになるでしょう。
広瀬◉なるほど、そういう意味では盲学校教育は面影の宝庫ですね。僕は、全国各地のボランティアが音訳(朗読)した専門書・小説・雑誌などの音声データを携帯型プレーヤーにダウンロードし、仕事に必要な情報を集めたり、余暇を楽しんだりしています。プレーヤーには常に複数の書籍データが入っていて、TPOに応じてそれらを取捨選択、「編集」しているということでしょうか。
耳で聞く読書の場合、音訳者の声とともにセリフが自分の体内に入り込んできます。単に情報が受動的に入ってくるというのではなく、特に小説ではストーリーに没入し、自分も登場人物の一人になっているような気持ちになります。聞き終わって(読み終わって)から数年経っても、主人公の面影が鮮明に残っていて、余韻を味わうことができます。ここは、前近代の日本人の平曲鑑賞に似ているのかもしれません。耳による読書は、慣れるまでは受動的になりがちだけど、経験を積めば能動的になっていくというのが僕の実感ですね。
松岡◉万葉以来の文芸作品や琵琶や三味線で作り上げる音曲には、面影を重視する歴史や営みがあったのだと思います。枕詞(ことば)で「たらちね」と言えば母が浮かんだり、「ひさかた」と言えば光が連想されたりしますが、そういった日本文化の面影を引き出す仕組みをうまく現代にも活用すれば、もっと豊かなイメージが得られたり、新しい世界が広がったりするはずです。そういう手法がもっと研究され、次世代に引き継がれていくことを私は願っています。
◎松岡正剛(まつおか・せいごう)
1944年京都市生まれ。「編集」をキーワードに執筆活動、書評サイト「千夜千冊」運営の一方、図書館・美術館・博物館が融合した角川武蔵野ミュージアム(埼玉県所沢市)館長。近著に『外は、良寛。』(講談社文芸文庫)。
◎広瀬浩二(ひろせ・こうじろう)
1967年生まれ。87年、京大初の全盲入学者。日本宗教史、触文化論。「さわる」をキーワードに新しい博物館展示のあり方を試行中。著書に『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』、近著に絵本『音にさわる』。
【対談シリーズを終えて】
広瀬浩二郎 氏
4月から対談シリーズを担当してきましたが、今回が最終回となります。松岡先生をはじめ、各回の対談相手のみなさんから、さまざまな示唆をいただきました。僕には対談相手の姿を直接視覚的に見ることはできません。しかし、対談してくださったお一人お一人の面影は、僕の記憶に深く刻まれています。考えながら言葉を選び、それをぶつけ合う対談は毎回エキサイティングで、相互接触から生まれる触発の大切さを再確認しました。そんな僕の「目に見えない」心の動き、知的興奮が紙面を通じて読者に伝われば幸いです。6回の対談シリーズが読者個々の記憶を刺激し、各人各様の面影を引き出すきっかけになることを願っています。半年間の連載企画にお付き合いいただき、ありがとうございました。
【特別展 ユニバーサルミュージアム さわる!“触”の大博覧会】
大阪府吹田市の国立民族学博物館で、2021年11月30日まで開催。水曜休館。視覚障害者が世界認識のベースにしてきた「さわる」行為を前面に押し出した展示会。「さわる」ことの実践によって、誰もが自分の知覚のあり方を問い直す機会となるだろう。図録に加え、民博の広報誌『月刊みんぱく』(2021年9月号)が広瀬浩二郎さんらの解説を収録し、展示の趣旨を理解しやすい。広報誌については民博友の会06(6877)8893へ。





