琵琶法師による歌や語りなど、全盲の人たちが手掛けた芸能が廃れて久しい。一方、室町時代に世阿弥が集大成し、当時の語り口で演じられる能は今も健在だ。古典芸能のルーツと未来をテーマに、全盲の文化人類学者・広瀬浩二郎さんと能役者・味方玄さんが語り合った。コーディネーターは、京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。
対談シリーズ
Conversation series
未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2021年第4回】
(2021年8月/京都市中京区寺町鞍馬口) ◉ 実際の掲載紙面はこちら

■対談
古典芸能 ルーツと未来
琵琶法師の精神を伝えたい
広瀬浩二郎氏(国立民族学博物館 准教授)
能、初心忘れず精進重ねる
味方玄氏(観世流能楽師)
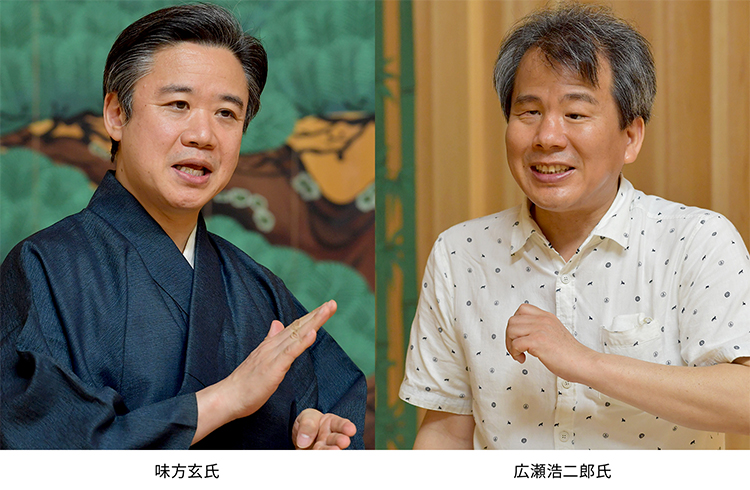
―広瀬さんに能舞台を体験いただきました。
広瀬◉能舞台に上がらせてもらうのは初めてです。最初は思っていたよりも狭いかなと感じましたが、一歩ずつ動いてみると意外に広い。足袋を履いた足裏でも、板の木目を感じることができるので、方向はある程度わかります。でも、足裏で木目を探っているようではまだまだなのでしょうね。
味方さんは能舞台の端に近づくと、温度が変化するとおっしゃっています。おそらく、空気の流れが変わるということなのでしょう。僕にはその変化が十分わかりませんでした。「言われてみたら、そうかなあ」というぼんやりした感じです。もっともっと身体感覚を研ぎ澄ませば、目が見えなくても舞台上を自由に動けるのかもしれませんね。
能は鎮魂の芸能ともいわれるように、怨霊をはじめ、霊の世界と密接に関わっています。目に見えない世界を大切にしてきた能楽師の味方先生とお話しする機会をいただき、たいへんうれしいです。
一緒に舞台上を動いてみて、味方さんの腰が決まっているというか、安定していることに驚きました。今日は役得で腰にさわらせてもらいましたが、動く際に腰のブレがまったくない。僕も趣味で武道に親しんできたので、丹田(下腹部)の大切さは理解しているつもりです。でも、味方さんの腰の動きは、僕なんかのへっぴり腰とはまったく違います。僕が力を込めて押しても引いても、びくともしない。
味方さんの丹田から、目に見えない気が発しており、その気が体内に満ちて、能の所作の原動力になっていることを実感しました。能楽師の所作の美しさ、力強さを触覚で確認できたのは貴重な体験ですね。
味方◉カマエとハコビを体験していただきました。私たちが能面をかけて演じる感覚を少し体感していただけたかなと思います。おっしゃる通り、気は体内だけに充満するだけでなく、舞台の板を通して大地から引き合うようなイメージです。今日は腰の部分を押さえていただいて抵抗を作り、ハコビをいたしました。そろーりそろーりと板をなでるように歩くのではないことが理解していただけたかなと思います。
広瀬◉盲目の旅芸人である琵琶法師や瞽女(ごぜ)は、江戸期までは全国的に活動していましたが、現在はその芸能の継承者がほとんどいません。一方、能は室町時代に観阿弥、世阿弥親子が登場し、飛躍的な発展を遂げ、今日でも独自の様式を持った舞台芸術として上演が続けられています。中世に起源を持つ同じような芸能ですが、前者は近代化とともに衰退し、後者は世代を超えて受け継がれてきました。「その違いは何だろう」という問題意識が僕にはあります。
まず伺いたいのは、世阿弥が記した「風姿花伝」に「花」という言葉が多く使われていますが、そもそも花とは何を指すのでしょうか。
味方◉世阿弥は父親や先人たちから受け継いだ奥義を後世に伝えるために「風姿花伝」を書き残しました。花は芸の真髄を表す言葉で、「舞台上の魅力」ということです。
広瀬◉琵琶法師や瞽女の芸能が衰退したのは、直接的には後継者不足が原因です。なぜ後継者がいなくなったのかと考えると、もしかすると伝統を死守することのみに注力し、本来の「花」を失ってしまったのかなとも感じます。「風姿花伝」には「花と面白きとめづらしきと、これ三つは同じ心なり」ともありますが、味方さんは古い演目を復活させるなど、新しい取り組みも積極的に行なっておられますね。
味方◉古いものをそのまま現代によみがえらせても、今を生きる人の心には響かないでしょう。演じ手も今をしっかり生きて、時代や社会の空気を感じ取り、作品を通して問題提起やアピールをしていかなければなりません。世阿弥もとっぴなことをするのではなく、いい意味で見ている人を裏切ることで、人との心に思いがけない感銘を起こさせる、それも「めづらしき花」だと言っています。
広瀬◉琵琶法師の「平家物語」は音と声による語り物、聴覚芸能の代表です。一方、世阿弥のすごさ、新しさは、「平家物語」などの古典に視覚的な要素を取り入れ、舞を充実させたところにあるのではないでしょうか。
味方◉世阿弥は、芸の基礎になるのは「二曲三体」であると記しています。二曲は基本技術である歌と舞、三体は老・軍・女の典型的な役柄のことを指します。世阿弥の座は元々、鬼や、例えば老人などの姿形を似せる「ものまね芸」からスタートしていますが、同時代のライバルだった能役者犬王の優美な舞を見て、世阿弥は自流の能にも取り入れます。また、観阿弥も鼓に合わせて歌い舞う「曲舞(くせまい)」のリズムを能の歌謡の中に織り込むなど様々、今につながる能の基礎を確立しました。


―能の物語には目の見えない人や身体の不自由な人が多く登場するようにも感じます。
味方◉能の作品「景清(かげきよ)」では、平家方の武将だった景清は九州に流されます。零落して盲目のこじきになった景清の元に一人娘が会いに来ます。娘との別れの名残に源平合戦での武勇を景清自ら語ります。ここには平家の人々の鎮魂を祈り「平家物語」を語る琵琶法師の姿が反映されています。また、「望月(もちづき)」には瞽女に扮(ふん)して敵を安心させ、仇(あだ)討ちの手助けをする女性も出てきます。
広瀬◉能や狂言など、中世芸能に盲人が多く登場するのは、彼らの存在が民衆の生活にとってなじみ深いものだった証拠といえます。盲人芸能者は全国各地を旅しており、その姿はさまざまな場面で民衆の生活に密接に関わっていたのではないでしょうか。
盲人芸能が衰退した原因を考えるキーワードとして、世阿弥の有名な言葉の一つ、「初心忘るべからず」を挙げることができると思います。世阿弥の残した伝書は、生き方の指針を示す人生の書としても読むことができますね。旅を続け、全国を歩くことによって琵琶法師や瞽女は「花」を獲得し、独創的な芸能を生み育ててきました。旅をする、歩くというのが彼らの「初心」だとすれば、近代以降、その初心を忘れてしまった側面があるのかもしれません。
味方◉芸には意識を怠ってはいけないポイントが数多くありますが、その一つ一つが世阿弥の言う初心に当たります。それが当たり前になり、舞台上で漫然とやってしまうと、横柄で自分勝手な芸になってしまいます。初心が連続しているのが芸であるという戒めを守り、精進を重ねていくと、本物の花が咲いた後に、なお花が残るような境地に至ることができるでしょう。それが能楽師として生きていく上での私の目標です。
世阿弥は役者として舞台に立つだけではなく、有力者の支援を取り付け、彼らが気に入る台本も書いていましたので、芸術家というよりは総合プロデューサーのような存在でもあります。世阿弥は「風姿花伝」は、一座を継続させていく求心力と考えていたので、「風姿花伝」は後継者と認めた一人に限定して相伝するとしていました。しかし、実際にはまず弟の四郎に与え、実子の元雅が成長すると彼にも授け、さらに娘婿にも伝えています。3人に与えていた事実には本音と建前が見え隠れし、世阿弥の人間らしさを感じます。
広瀬◉1990年代、大学院生だった僕は琵琶法師や瞽女のほか、盲目の霊媒師であるイタコの調査をしていました。文字を媒介としない語り物の伝承、死者の霊に代表されるような目に見えない世界との交流が、前近代の盲人芸能の特徴です。1990年代は、こういった盲人芸能の最後の継承者たちが細々と活動していた時期です。21世紀に入ると、「最後の琵琶法師」「最後の瞽女」と称される盲人芸能の担い手が相次いで亡くなります。今日、視覚障害者の生業(なりわい)としての琵琶法師・瞽女・イタコは消滅しました。
瞽女は旅を続けながら、河原などで大きな声を出して唄(うた)の稽古をします。のどをつぶし、血が出ても声を出して、声帯を鍛えたそうです。瞽女の声は空気を振動させ、多くの聴衆を魅了しましたが、その発声法は西洋音楽とはまったく異なるものです。旅の中で、自然と触れ合い、天地万物につながる声を獲得する。声は、目に見えない世界に入るための武器であり、その声を鍛えるために、旅は必要不可欠だったのだと思います。琵琶法師や瞽女の実地調査を通じて、旅すること、歩くことが彼らの芸能に奥行きと豊かさを与えていたと実感しました。
味方◉私は入門したときから声が細いと繰り返し指摘されていましたので、今もそれを戒めに強く声を出そうと意識しています。それぞれに最適な身体の使い方があるはずなので、謡い込んで、それを発見するのが重要だと考えています。ところで、瞽女や琵琶法師は市場など人の集まる場所にとどまって芸を披露することもあったのでしょうか。
広瀬◉現在のストリートパフォーマンスと同じで、人が集まる所で芸能を披露し、金銭を得る例は多かったはずです。旅を続けるためにはお金や食料が必要なのだから、それらを比較的容易に得る手段として、貴族や寺社などのパトロンを探す。どこに行けばお金や食べ物が得られるのか、芸能者間で情報がやり取りされていたでしょう。中世の市は芸能者のたまり場、情報交換の拠点ともなっていたわけです。
江戸時代以降は瞽女の組織が確立し、門付けが基本となります。まず、村内の各家の出入口付近、門の前に立って芸を披露し、瞽女が村にやってきたことを伝えます。村を巡って芸を披露した後、夜になると村民たちが集まる宴会に招かれます。瞽女唄は暗く悲しいという印象が独り歩きしていますが、実際には陽気で楽しい瞽女唄もたくさんありました。宴会を盛り上げるためには、多彩な唄のレパートリーを持っていることが大切です。
平均的な瞽女は、1年のうち、300日くらい旅をしていました。どこを訪ねるのかという年間スケジュールはだいたい決まっています。たとえば、新潟など、寒い地域の瞽女は、冬には温暖なエリアを回るか、家で稽古に励んでいました。深い雪の中を盲目の瞽女がとぼとぼ歩くというイメージは、映画のシーンなどで誇張された部分があります。
瞽女が訪問するのは農村です。厳しい農作業が続く日常生活の中で、瞽女がやってくるのは特別な出来事、「ハレの日」なので、彼女たちは村民に歓迎されました。なぜ、目の見えない琵琶法師や瞽女が、危険を伴う旅にあえて出たのか。これは素朴な疑問ですし、僕の調査でも何度も同じ質問をしました。僕がインタビューした盲人芸能者の答えは単純明快です。「待っている人、歓迎してくれる人がいるから、多少苦労してもその村を訪ねるんだ」。この発言こそが盲人芸能者の「初心」であり、「花」を育てるバイタリティーの源泉だと思います。
味方◉瞽女たちの役割は、古来より神楽を舞ったり、神託を得て他の者に伝えたりする巫女(みこ)とも重なりますね。
広瀬◉盲人芸能者は、古代の来訪神を意味する「まれびと」の系譜に位置付けることができます。定期的に村を訪れる瞽女は、別世界からやってくる、ありがたい人と認識されていました。僕が調査した九州の琵琶法師は盲僧と呼ばれており、宗教と芸能が一体となった独自の儀礼を執行していました。読経や祈祷(きとう)の後、琵琶を弾きながら、さまざまな語り物を披露し、人々を楽しませます。カウンセラーでもあり、エンターテイナーでもあるわけです。瞽女や琵琶法師は特別視される一方で、民衆の実生活にとって身近で不可欠な存在でもありました。この感覚は、近代的な差別とは明らかに異なります。
味方◉イタコの取材では、何かが憑依(ひょうい)するようなことが目の前で起こったりするのですか。
広瀬◉青森県の恐山で出会ったイタコは、本物の霊媒師だと感じました。初対面なのに、僕の個人情報を言い当てられ、ちょっと怖かったですね。そのイタコは、「自分がしゃべるのではなく、体内に入り込んだ霊の言葉が無意識のうちに口から出るだけ」と言っていました。1990年代には、霊感の鋭いイタコがまだ複数おられました。
僕はよく「目の見えない者は、目に見えない物を詩っている」と言います。盲目のイタコは、現実世界では目が見えないわけです。でも逆に、視覚に頼らない強みを活かし、肉眼では見えない霊界にアプローチすることができるともいえます。世界各地では、祭儀の際にシャーマン(呪術者)が目を閉じて集中力を高める事例が数多く報告されています。いわば、疑似盲目状態を作って、霊を招き寄せるのですね。古今東西、宗教儀礼などで用いられる仮面の視野が極端に狭いことが、以前から気になっていました。能面もそうですね。これは、視野を制限することによって五感が錬磨され、集中力が増すという理解でよろしいでしょうか。
味方◉能面をつけて舞う方が集中力は格段に上がります。ただ、視界は極小さなポイントしか見えません。能面を着けて実際の視線で周囲を見ようとすると、能面は不自然な角度になり、演技や姿勢は崩れてしまいます。そういった制約があることで何か特別な力が宿るような気がしますし、自分の意思で舞っているというよりは、身体が自然に動き、舞わされているような感覚にもなります。
広瀬◉イタコの場合、首に掛けた長い数珠をまさぐりながら呪文を唱えることで、トランス(忘我)状態に入ります。触覚(手)と聴覚(声)が、目に見えない世界、霊界に入る扉を開くわけです。
味方◉能の「葵上(あおいのうえ)」では巫女が登場し、梓(あずさ)弓を弾き鳴らしながら、神霊を呼び出すための歌を歌います。巫女の場合は梓弓がトランス状態になるための道具になっているようです。
広瀬◉梓弓は触覚で奏で、聴覚を刺激する呪具ですね。「耳なし芳一」の怪談を想起するまでもなく、弦楽器である琵琶も、神霊を招き寄せる機能を有していました。
―味方さんは先日、室町時代の作品「篁(たかむら)」を500年以上の時を経て復曲させましたが、今後どう芸や能の魅力を伝えていこうと考えていますか。
味方◉室町時代に上演記録があり、台本も今に伝わっているのに、なぜ長期間、上演されることがなかったのかという問題意識から、「篁」の復曲に取り組むようになりました。ただ、室町時代と現代とは上演場所や環境のほか、衣装なども異なりますので、本当の意味での復活とは言えないかもしれませんが、演目が持っている本質を現代にどう再現し、伝えていくかは心掛けたつもりです。
―いったん絶えた琵琶法師や瞽女の今後をどうお考えですか。
広瀬◉視覚障害者の職業が多様化した21世紀において、琵琶法師や瞽女の後継者がいないのは「歴史の進歩」ととらえることができるかもしれません。琵琶法師の平曲や瞽女唄は伝統芸能として継承されるとは思いますが、その担い手として視覚障害の当事者が活躍するのは難しいでしょう。今は「障害者も、健常者と同じことができる」という価値観が主流で、そういった意識を持つ当事者が増えています。
僕は自分のことを「琵琶を持たない琵琶法師」と称しています。僕自身が琵琶法師の芸を受け継ぎ、「まれびと」となって各地を巡り歩くことはできません。しかし、琵琶法師の精神、目に見えない世界を大事にする文化を後世に伝えていくのが自らの役割なのかなと考えています。自分の研究、博物館での仕事にどうやって「花」を咲かせることができるのか、迷った時は琵琶法師や瞽女の原点に立ち返る。1990年代の盲人芸能者との出会いが、僕にとっての「初心」ということになりますね。
味方◉芸能を伝えていくには、まず自分たちが生き生きと新鮮に舞台で演じ、若い世代の人たちがやりたい、見たいと思う魅力的なものでなければと考えます。今や映像や音楽はスマートフォンなどで簡単に見聞きできます。あくまでも間口は広く、しかしその芸能の持つ空気感を、直に肌で感じてもらえる機会をできるだけ多くつくっていきたいと考えています。
◎広瀬浩二郎(ひろせ・こうじろう)
1967年生まれ。87年、京大初の全盲入学者。日本宗教史、触文化論。京大で居合道部。合気道二段。ブラインドサッカーにも参加。9月から大阪府吹田市の国立民族学博物館で特別展開催予定。
◎味方玄(みかた・しずか)
1966年生まれ。観世流シテ方。実家の十念寺は、能を愛好した6代将軍足利義教の建立。片山幽雪さんの内弟子となり、今年は独立30年。室町時代の能「篁」を500年を経て復曲披露。著書に「能へのいざない」(淡交社)。

