立場や文化的な背景を超え、人はどこまで理解しあえるのか。京都発のメッセージ企画「日本人の忘れもの知恵会議」で、文化人類学者・広瀬浩二郎さんが、大学の同級生で歴史学者・岩崎奈緖子さんと他者を理解することの難しさ、面白さを語り合った。コーディネーターは京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。
対談シリーズ
Conversation series
未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2021年第2回】
(2021年6月/京都大総合博物館) ◉ 実際の掲載紙面はこちら

■対談
「他者理解の先にあるもの」
復活させたい違い認める寛容さ
広瀬浩二郎氏(文化人類学者)
アイヌの歴史に近づくよう研究
岩崎奈緖子氏(歴史学者)
岩崎◉ここは、1987年に京都大に入学した私たちが3、4回生の時に古文書演習で使っていた畳敷きの部屋です。当時は、文学部博物館でしたが、今は文学部から離れて、総合博物館という組織に変わりました。
広瀬◉この部屋には少しほろ苦い思い出があります。古文書演習はくずし字で書かれた文字を読解していく授業ですが、大げさに言えば、目の見えない僕にとっては人生最大のピンチでした。大学受験、一般教養科目の教科書など、それまでは通常の文字を点字にしてくれる支援者がたくさんいました。「目が見えなくても何とかなるさ」と思っていましたが、さすがに古文書には手も足も出ませんでした。
前例がないので、自分で古文書との付き合い方を考えるしかないわけです。担当教員とも相談し、最終的に僕はこの部屋で学ぶ同級生から一人離れました。当時、パソコンの画面読み上げソフトが普及し始めており、大学院の先輩に古文書をパソコンに入力してもらいました。僕は別室で、そのデータを一文字ずつ音声で聴いて確認します。さらに、それを自分で点字にして解釈します。時間はかかりますが、一つ一つの史料の重みを実感しました。今の学生たちにとって新型コロナウイルス感染拡大はピンチですが、同時に新しいことに踏み出すチャンスでもあると捉えてほしいと思います。コロナ禍をこれまでの勉強法、生活スタイルをじっくり見つめ直す機会にしてもらいたいですね。
ところで、岩崎さんはなぜ京都大を受験したのですか。
岩崎◉元々、民俗学に関心があって、現地に赴いて調査するフィールドワークに憧れていました。民俗学をやるなら歴史のことが分かっていた方がいいと助言され、日本史を専攻しました。
私は短大卒業後、4年間の会社員生活を経て、1年間予備校に通いました。勝算なく始めた浪人生活でしたが、OLの頃よりも毎日はよほどおもしろかったです。運良く入学できた京大では、定年後に入学してきた人もいて、現役入学者とは7学年違いですが、違和感や孤独感はありませんでした。
広瀬◉僕の場合は東京で生まれ育ったので、京都に来た一番の理由は親元を離れたかったからです。何もできないくせに、いや何もできないからこそ、一人暮らしに挑戦したかった。司馬遼太郎が好きで、戦国時代や幕末の歴史に興味があったので、日本史を学ぶなら京都の大学がいいなと考えていました。
もう30年以上も前になりますが、京大に入学した初めての全盲学生ということで、まずメディアからの取材攻勢がありました。「有名人になったぞ!?」という単純な喜びがある一方で、「京大入学者は2千人以上いるのに、なぜ僕だけが特別扱いされるのだろう」と、疑問も感じました。
大半の同級生は、全盲の人と接するのが初めてです。階段は一人で上がれるのか、食事はどうするのかと質問攻めにされました。僕にとって当たり前のことでも、同級生は「すごいね」「たいへんだね」と素直な感想を述べる。入学後の数カ月は、視覚障害に対する過大評価と過小評価の連続で、フラストレーションが募りました。
ただ、学内は全体的にのんびりしていて、当時の文学部は休講も多かった。勉強も遊びも、時間の使い方は自分で決めるという意識が強かったと思います。「大学とは、自分で勉強する所だ」と明言する教官もいました。大学で「自分」を鍛える時間が与えられたのは幸福なことですし、京大の自由な雰囲気は僕に合っていました。
岩崎◉2020年度はオンライン授業が中心で、大学構内に立ち入ることさえ難しい時期が続きました。人と接する機会が失われてしまうことは、学生の人間形成において非常にマイナスだと思います。生協で一緒にご飯を食べる、ゼミの発表で恥ずかしい思いをする、そういう何気ない経験が若者には大切ですね。
広瀬◉2020年度の後期、京都市立芸術大でオンライン授業を担当しました。作品制作をする演習なので、本来は対面授業で、僕も実際に学生の試作品に触れてアドバイス、評価をするのが原則です。でも、昨年度はオンラインで学生に作品のコンセプトを説明してもらう形式になりました。学生個々が「言葉」を磨くトレーニングにはなったと思いますが、制作系の授業をオンラインで進めるのはきつかったですね。一部の学生たちはオンライン授業の傍ら、時々大学にも出てきていました。少人数で集まり、お互いの作品を見せ合ったりしながら、制作に励んでいました。
結果として、一人で自宅にこもって制作した学生よりも、友人と一緒に切磋琢磨(せっさたくま)して作業を進めた学生の方が、面白い作品を完成させたかなと感じました。一人で黙々と手を動かすのが性に合っている人もいますが、やはり友人との交流は重要です。僕はよく「非接触から触発は生まれない」と言っています。僕が学生のころ、授業には出ないが、サークルのボックスには顔を出す、なんてことが度々ありました。もちろん、感染拡大予防は大事だけど、学生にとって大学構内に入れないことは、いろんな意味で厳しい事態ですね。
岩崎◉ものづくりをしたり、考えたりすることは、言い換えれば、自分を表現することであって、誰かと競い合ったり、評価されたり、時には批判されたりすることを通じて、自分自身が何なのかを確かめているところがあります。作ったり考えたりしている時、多くの人は自分一人で取り組んでいると感じていると思いますが、それは錯覚で、実は、無意識のうちに、外部からの影響をはね返したり、受け入れたりしながら、自分自身に向き合い、思考を深めているんですよね。オンラインにもいい所はありますが、情報だけのやりとりに終始しがちな印象があって、もし大学のオンライン授業がそうなってしまったら、学生はケージの中でエサを与えられているブロイラーと同じではないかと心配です。
広瀬◉大学の同級生たちとの交流の中で、視覚障害者である自分の存在意義を考えるようになりました。まあ、そういうと少々大げさですが、昔の盲人たちも「すごいね」「たいへんだね」と言われていたのか、興味がありました。僕の研究は、盲目の宗教・芸能者である琵琶法師や瞽女(ゴゼ)の調査から始まっています。1990年代には現役で活躍している盲僧、盲巫女(イタコ)が九州や東北地方におられたので、各地を訪ね、聞き取り調査を重ねました。
歴史をさかのぼっていくと、前近代の社会では文字を使える人が少数派です。社会の多数派は文字を使わず、主に音と声で情報を入手・共有する時代が長く続きます。音や声による歴史は、古文書に直接記録されることがありません。古文書を読み解くという点でハンディがある僕は、前近代の盲人をはじめ、無文字の社会・文化に関心を持つようになりました。文字を使わない手法で、文字を使わない人々の歴史にアプローチするということです。当然、僕の調査では聴覚情報(音声)と触覚情報(実体験)が重要となります。
一方、岩崎さんはアイヌ民族の歴史研究の専門家です。文字を持たないアイヌの人々について、数少ない文字資料から彼らの社会・文化の実態を明らかにしようと研究を重ねていますね。
岩崎◉私が専門とするのは江戸時代ですが、近代に入ってアイヌの人たちの社会は大きく変化させられており、母語としてのアイヌ語も一度失われているので、広瀬君のように、聞き取りから江戸時代のアイヌの人々の暮らしを再構成することはできません。
じゃあどうするのか。アイヌの人々が自ら書き残したものはないにしても、日本やロシアや中国の人たちが、記録を残しています。もちろん時代が時代ですから、偏見に満ちた内容ではあるわけですが、私は偏見の向こうに豊かな世界が広がっていることを信じていて、そういう誰も知らない世界を行間から探り当てたいと思い研究を続けています。
ただ、日本には、江戸時代以来、アイヌの人々の歴史は虐げられた歴史として描かれる伝統があります。だから私が、いやいや江戸時代の蝦夷地(北海道のこと)での和人(本州以南から出向いた人々)の暮らしは、アイヌの人々の習慣やルールを尊重しないと成り立たなかったんですよ、というようなことを主張すると、それはおかしいという反応が返ってくるんですね。
さっき、広瀬君から畳の部屋にまつわる思い出を聞いて、何と言ったらいいかわからない気持ちになりました。私には歴史研究者への道のスタート地点として、甘酸っぱい思い出がいっぱいの場所でしたから。30年以上たって、ようやくその懸隔に気づいた。他者を知ることの難しさを思います。そしてそのことは、私がアイヌの歴史を書くことの困難にもつながっていると感じます。どうしたら他者である彼らの歴史に近づくことができるのか。切実に思いながら、アイヌでない人々の書き残した記録を読み込んでいくしかないと思っています。

広瀬◉点字は1824年、パリの盲学校の生徒で、自身も全盲だったルイ・ブライユによって考案されました。近年ではルイ・ブライユが日本の小学校で国語教科書に取り上げられるようになり、日本の子どもたちの間で、ちょっとした有名人になっています。近代化とともに点字は世界に広がり、各言語への翻案がなされます。明治維新後の日本にも導入され、1890年には日本語の点字が誕生しました。
近代社会では、文字を使える人が多数派となります。それまで、文字を使わないことで個性を発揮していた視覚障害者たちは、徐々に文字を使えない人々として差別されるようになるのです。だから、19世紀に世界の視覚障害者たちが「点字=文字」を獲得した意義はきわめて大きい。多数派への仲間入りが可能になったわけです。点字は単なる文字というレベルにとどまらず、点字受験・点字投票などの例からもわかるように、視覚障害者の市民権拡充にもつながっています。僕自身が大学に進学し、博物館に就職できたのも、点字のおかげといえます。点字考案から200年。視覚障害者たちはルイ・ブライユから計り知れない恩恵を受けてきました。
一方、点字の普及が視覚障害者にもたらした負の影響にも注目しなければなりません。点字は視覚障害者の「完全参加と平等」を実現する有力なツールですが、「健常者と同じことができる」という意識が強くなると、「健常者と同じことをしなければならない」という強迫観念を引き起こしかねません。多数派との違いを尊重する精神風土から、琵琶法師や瞽女の生業(なりわい)が生まれ、発展しました。近代化によって、「違い」を認め合う豊かさ、寛容さがなくなったのは確かでしょう。
少数派である障害者は、一般社会に仲間入りするために頑張らなければならない。いや、より正確には頑張らざるを得ないわけです。当然、頑張れなくて近代化から見捨てられる人、あるいは自ら離脱する人も出てきます。「オウム真理教事件」の麻原彰晃は、熊本県立盲学校出身の視覚障害者です。彼の劣等感、「健常者に追い付け追い越せ」という切迫感が、オウム事件の一因になったのは確かだと思います。麻原を弁護するつもりはありませんが、一面において、彼は近代化の犠牲者だったともいえるでしょう。
2024年の「点字考案200周年」には、世界各国でさまざまな記念行事が実施されるはずです。単なるお祭りではなく、点字が視覚障害者に与えたもの、その功罪をしっかり検証する機会にしたいと考えています。
岩崎◉パソコンやスマホが急速に発達し、目の不自由な人が学ぶ環境は良くなっていると感じますが、広瀬君はどう見ていますか。
広瀬◉パソコンのキーボードで入力、画面の情報を音声で確認する「点字ワープロ」が開発されたのは、ちょうど僕が大学に入学したころです。このソフトを使えば、僕たち点字使用者が通常の漢字仮名交じり文を書けるようになりました。今では視覚障害者のインターネット利用は当たり前となり、スマホユーザーも増えています。僕自身の仕事でも、Eメールの送受信に日々かなりの時間を使っています。僕がメールを送る人の9割以上は、点字を知らない健常者です。文字を使わなかった時代、点字しかなかった時代に比べると、隔世の感がありますね。現在の大学で学ぶ障害学生は恵まれているなというのが素直な感想です。
ただ、単純に情報処理の量を比べると、目が見える人(視覚)には太刀打ちできません。触覚や聴覚で情報を得る視覚障害者は、やはり量ではなく質にこだわるべきでしょう。目が見えないからこそ、健常者(多数派)が見落としていること、見忘れていることを「発見」できる。僕はそう信じています。
昨今の障害児教育、あるいは大学の障害学生支援などでは、「健常者と同じことができればいい」という風潮があります。それを全否定はしませんが、むしろ見えない、聞こえないなどの「違い」を強みとして生かすべきだと思います。
岩崎◉目が不自由な人だけではなく、より速く、スマートにと、常に効率を求められているのが今の時代です。学生時代、京大では日本史の卒論は原則手書きで、ワープロの使用は認められていませんでした。先生たちは手を使って書くことによって、本当に必要なことを見極め、推敲(すいこう)を重ねて無駄なものをそぎ落とし、最終的に論文のエッセンスが磨き上げられると考えていたのでしょう。
30年前と比べると、文字を書く機会は減っていますし、今はキーボードすら使えない子どももいます。人さし指1本で操作できるスマホはとても便利ですが、失っているものは計り知れないような気がします。
広瀬◉効率と便利さの追求ということで、僕が想起するのは観光旅行です。今、観光庁は「誰もが気兼ねなく参加できる旅行=ユニバーサルツーリズム」を普及させる取り組みに力を入れています。高齢者・障害者・外国人など、いわゆる社会的弱者が参加しやすいツアーを増やせば、トータルとしてユニバーサルが実現できるという発想です。旅行社にとって顧客が増えるのは悪いことではないし、結果的に重度障害者が旅行を楽しめるようになればすばらしい。でも、今の視覚依存の観光旅行は効率重視です。そこにどうやって、どれだけ高齢者や障害者が入っていけるのかという個別対応を積み重ねても、ユニバーサルにはならないような気がします。
例えば、目の見えない人と一般のツアー客が一緒に旅をするとします。現状のユニバーサルツーリズムの考え方では、点字の資料や音声ガイドを準備して、見て学ぶ、見て楽しむ要素を視覚障害者に伝えようとします。いわば少数派の多数派への同化です。その方が効率がいいわけです。
では、視覚障害者がいることをきっかけとして、見るのではなく、触れる要素を積極的に取り入れてみるのはどうでしょうか。手で文化財の感触を確かめたり、自然を全身で体感するツアーが考えられます。触覚は視覚よりも時間がかかるので、情報伝達の効率は劣ります。しかし、少数派の「見方」を多数派が取り入れるのも新鮮でしょう。そこから、新たな「ユニバーサル=普遍的」観光旅行が生まれるはずです。常識的な発想、既存の価値観を変えていくためのキーワードが「ユニバーサル」だと僕は思います。
岩崎◉国が進めている観光振興策は危ういというのが率直な印象です。高齢者や障害者への配慮が求められる理由は、お金を落としてくれる消費者だからです。インバウンド向けの多言語化と根元は同じです。広瀬君は博物館を舞台に、ユニバーサルという理念の下、価値観の変革に挑戦しているわけですが、国は、地方創生という理念の下、お金を地域に落とすために、博物館を観光地に変えようとしている。水と油ですよね。
博物館は、生涯にわたっての学びを提供する場です。法律にもそう書いてあって、私はそう信じてきました。しかし、広瀬君は、博物館のあり方そのものを変えようとしている。人間の感性を視覚から解き放ち、本質をつかみ取る場として、博物館の存在意義を刷新しようとしている。これは広瀬君でなければできない挑戦で、健常者も巻き込んだ大きなうねりが起こっているのを見ると、広瀬君は「現代の琵琶法師」ではと感じています。
広瀬◉同級生の岩崎さんに「現代の琵琶法師」と言ってもらえて光栄です。これからもお互いに、ミュージアムを拠点として、歴史を書き換える、さらには歴史を創り出すような仕事をしていきたいですね。
≪メモ≫
対談のゲスト、岩崎奈緖子・京都大博物館教授の最新刊『近世後期の世界認識と鎖国』(吉川弘文館)が2021年6月に刊行された。「他者理解」を外交の尺度で考察しており、広瀬浩二郎さんとの対談理解を突っ込んで理解する参考になる。
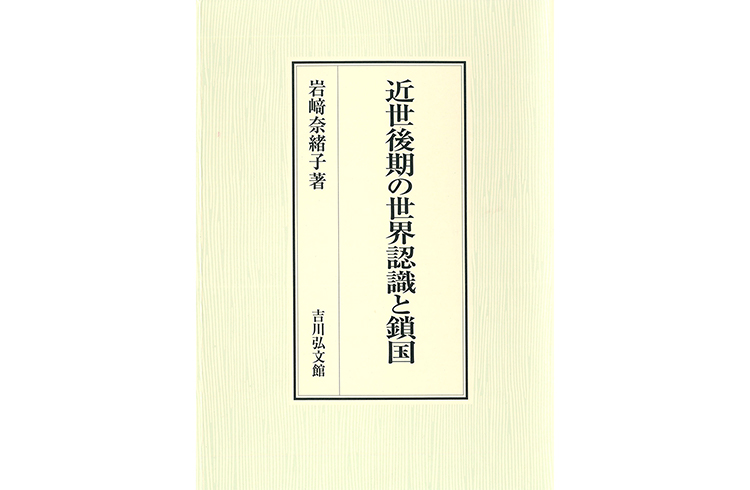
徳川の平和を堪能していた幕府が黒船にあわてふためき、開明的な薩長によって打ち倒されて近代化が始まる―かつての日本史の教科書に掲載されていた図式が塗り替えられて久しい。実際には18世紀ごろには諸外国が日本列島のあちこちに姿を見せ、幕府は対応に知恵を絞っていた。放映中のNHK大河ドラマ「青天を衝く」でも有能な幕僚が登場する。幕府と諸外国との接点がなかったわけでは決してない。
本書は、江戸中期以降の幕府の対外政策に影響を与えた蝦夷地=北海道からカムチャッカ半島、ユーラシア大陸を中心に描いた地図に着目。年代や制作者が異なると、地図上の現在のロシアに相当する地名(国名)表記が異なるのはなぜか(例えば「おろしあ」)。史料を通じ、表記変遷の過程を追う。
地図情報の編集者、政策立案に当たった松平定信らの目には、どんな世界が見えていたのだろう。結論を簡単に紹介すると、西欧から極東に広がる強大な「おろしあ」国が日本列島のすぐそこに迫っている事実だ。秀吉や家康ら16~17世紀の権力者の視線との違いは「南蛮」ではなく北方のアイヌやロシアに目を向けたことと、交易よりはむしろ交戦の可能性を意識した緊張関係だったことだろうか。
興味深いのは「打ち払い」だ。打ち払うことで国境が意識される。蝦夷地を幕府の所管するエリアに組み込むかどうか、海防の権限を大名に委ねるかどうか。外部を意識したことで、日本という国が形づくられたともいえる。
学術書だが論旨をたどれば、教科書レベルの知識があれば順を追って楽しめる。本書の大きなキーワード「鎖国」のように、研究者には常識の部分も、初出史料と意味の成立過程が丁寧に解説されているからだ。
独自の史観を展開する渡辺京二『黒船前夜』(洋泉社新書)、12世紀の平泉から北方世界を考える小島毅『義経の東アジア』(文春学芸ライブラリー)、『「鎖国」を見直す』(岩波現代文庫)が関連書として入手しやすく、参考になる。
◎広瀬浩二郎(ひろせ・こうじろう)
1967年生まれ。87年、京大初の全盲入学者。日本宗教史、触文化論。2001年に国立民族学博物館へ。現在は准教授。著書に『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』(小さ子社)など。
◎岩崎奈緒子(いわさき・なおこ)
1961年生まれ。日本近世史。2001年に京都大総合博物館着任。館長も務めた。著書に『近世後期の世界認識と鎖国』(吉川弘文館)。「京都・大学ミュージアム連携」で共同展示にも尽力。

