京都から新しい暮らしと文化を考えるキャンペーン企画「日本人の忘れもの知恵会議」。文化人類学者小川さやかさんがホストのオンライン連続対談も最終回だ。テーマは「コロナ禍の向こうに見える暮らし」。旧知の上野千鶴子さんと、人間関係のあり方などを自由に語り合った。コーディネーターは京都新聞総合研究所所長の内田孝が務めた。
対談シリーズ
Conversation series
未来へ受け継ぐ Things to inherit to the future【2020年第4回】
(2020年10月/オンライン) ◉ 実際の掲載紙面はこちら

■対談
コロナ禍の向こうに見える暮らし
上野千鶴子氏(認定NPO法人WANウィメンズアクションネットワーク理事長)
小川さやか氏(文化人類学者)
地域や会社を離れた縁いかが 人や社会との関係にこそ投資
小川◉新型コロナウイルス感染拡大という危機を受け、すでに平時に起きていた矛盾や問題が鮮明化し、より拡大する傾向にあります。私たちの生活も大きく変わってきていますね。アフリカのタンザニアの事例も基に、問題解決のカギを考えてみたいと思います。
上野◉オンライン上のツールや仕組みの普及が大きく加速しました。通勤や移動の必要がなくなり、多くの人にゆとりが生まれました。これまで時間や金銭的なコストだけではなく、心身への負担も大きかったのだとつくづく感じます。
小川◉文化人類学者としては海外調査中にも日本の大学生向けのリモート授業が可能になるのではないかと大いに期待しています。
上野◉今回の自粛生活で、介護や公共交通、宅配など社会に不可欠な仕事に従事するエッセンシャルワーカー不在では、私たちの暮らしは1日たりとも立ち行かないことを再確認しました。彼らのおかげで物流は滞らず、ごみ収集も途絶えませんでした。そのことにたいへん感動しました。ただ、「オンライン階級」という言葉も生まれており、現場での作業や対応業務に従事するエッセンシャルワーカーと、オンラインを活用して業務をこなしている人の間で格差が広がっているようです。
小川◉そうですね。エッセンシャルワーカーが抱える困難にはもっと目を向ける必要がありますね。ところで、女性が結婚、出産した後も働くことが当たり前になり、共働き世帯が増えました。上野さんはテレワークによる職住一致により、夫婦ともに自宅で仕事をするようになったことで、家庭内での性別役割分担が再調整されていくと指摘されていますね。
上野◉夫婦ともに自宅で仕事をしていると、どうしても夫が優先され、妻のテレワークはキッチンの片隅に追いやられている家庭が少なくありません。妻の仕事は子どもの世話で寸断されます。家の中で一人になれる場所がないという声もよく耳にします。一方で、夫は日常生活がいかにして成り立っているか、昼間に子どもが何をして過ごしているかを初めてその目で見ることで、夫婦間で暮らし方全般の見直しが起こり、役割分担も変わってきています。それ以前から夫と妻がラインでやりとりしている家庭もすごく多いですね。画面を通した会話だから言えることもありますし、直接の対話とオンラインをうまく使い分けているようです。
小川◉結婚している、していないにかかわらず、老後を一人で過ごす、いわゆる「おひとりさま」も多くいます。コロナ禍によって、おひとりさまの生き方にも変化はあるのでしょうか。
上野◉私は2007年に「おひとりさまの老後」を刊行し、同じシリーズで何冊か出版しました。ひとりでいても平気というのが「おひとりさま力」。今回の自粛生活でも特に人に会いたいと思いませんし、会わなくても平気だということが自分でもよく分かりました(笑)。だからといって孤立しているわけではありません。老後を楽しく、心地よく生きるための支えになるのは友人や仲間との交流ですから、オンラインの会議システムを使って女子会もよくやっていますよ。
小川◉オンラインで仕事の打ち合わせなどをしていると、相手の暮らしぶりが垣間見えることがあります。子どもの姿が画面に映ると、この人は家ではこんなふうにお母さんをしているのかと関心を抱いたりします。些細なことですが、そんなことが多様な働き方への理解につながるといいと期待しています。
上野◉今後、職住一致が定着すれば都心部のオフィス需要は減り、賃料も下落するでしょう。午前9時から午後5時を勤務時間と定める必要性も薄れ、例えば子どもを寝かしつけた後の夜中に仕事をするなど、時間の自己管理もできるでしょう。
高度経済成長期以前は農業や自営業など職住一致の世帯が多くありました。通勤電車に揺られ、多くの人が都心のオフィス街に通う職住分離の近代は、長い文明の中では一過性の時代にすぎなかったといわれる日が来るかもしれません。
小川◉職住一致で、住む場所を自由に選んだり、生活スタイルを自分でデザインできたりするようになると、より心地よく、自然な暮らしができるようになりますね。
上野◉職住一致の基盤を支えている働き方の一つは、個人が単発の仕事をネット経由で請け負うギグエコノミーです。小川さんが長年、現地調査を続けてきたアフリカ・タンザニアの行商人マチンガの人たちがインターネットを通じて商品を売買するような可能性はあるのでしょうか。
小川◉先進諸国では、ギグエコノミーは自由度が高いものの、企業に雇用された時のような保障が得られないといった問題とともに議論されがちですが、アフリカ諸国の都市部では零細自営業者が多く、従来の働き方を拡張するものとしてギグエコノミーが普及しつつあります。マチンガの人たちはもともと顧客の用事や注文を聞いて回る御用聞きと、無理やり商品を売りつける押し売りの中間のようなビジネスをしていました。インターネットとの相性は抜群で、すでにオンラインで注文を受けて顧客の元に商品を届けたり、店で商品を試着している様子の動画を見せて顧客に商品購入を勧めるといった多様なギグエコノミーの形態が生まれています。
上野◉小川さんが『思想としての<新型コロナウィルス禍>』(河出書房新社)に寄稿したエッセイを読んで、タンザニアの人たちのビジネススタイルで面白いと感じたのは、輸入が途絶えるとか、対面販売が難しくなるとか、危機が訪れると直ちに投資先を変えて生き延びているところです。
危機のなかで生き延びるのはサブシステンスエコノミー(生存を支える経済)ですね。今、日本では農業分野のベンチャー企業で多くの女性が活躍しています。コロナ禍の厳しい経営環境の中で、飲食店や学校給食向けに食材を生産していた業者は苦戦を強いられていますが、彼女たちは2割増しで業績を伸ばしているといいます。
末端消費者と直接取引をして、産地から新鮮な野菜を届けるという事業スタイルで、外出を控え、自宅で食事を楽しむ人の需要に応えています。
小川◉生活や暮らしに関わる分野への投資は今後、さらに重要になると私は見ています。タンザニアではお金にあまり信用がないので、現金が手元にあればすぐに食べ物と交換します。さらにお金に余裕があれば家畜や農地を購入します。貯金もしますが、銀行に預けている間、ずっと同じ価値であるかどうか分からないと多くの人は考えています。
上野◉私は働く女性のサバイバル戦術として「ゴー・バック・トゥ・ザ・百姓ライフ」という考え方を提案してきました。百姓は「百(くさぐさ)の姓(かばね)」とも読み、稲作や畑作だけではなく、さまざまな職業の組み合わせを意味します。昔から農閑期には出稼ぎに行ったり、炭焼きや機織りで現金収入を得たりしていました。近年は従業員に副業を認める企業も増えていますし、複数の仕事を持つことが以前よりも容易になってきました。
小川◉タンザニアの人たちは事業規模が大きくないため、何かあった時にはすぐに転換できるということもありますが、そもそも付き合っている人が多様であったことが変化に柔軟に対応できている理由でしょう。また彼らの多くは、日本人のように貯蓄に励む代わりに、多様な小商いに投資します。そこからも人間関係が広がります。お金の貸し借りは頻繁に行われますが、特に返済期限はなく、お金に困ると自分がお金を貸した相手から取り立てるよりも、余裕のある別の相手に借金を申し込みます。余裕がある人から余裕がない人へ何となくお金や物が回っていくセーフティーネットのようなものがあり、そこから脱落しない限り生きていくことができます。ビジネスでは事業の秘訣を教えたり、取引先を紹介したりして、商売仲間と緩やかなつながりを持つことで、失敗しても誰かが助けてくれ、再挑戦もできる仕組みがあります。
上野◉その話を聞いて思い浮かぶのは、非合法に設けられ、食料品などの取引をしていた敗戦後の日本の闇市です。物資不足で混乱が続き、公権力の統制もない弱肉強食の世界では、タンザニアの人たちのような助け合いがあったとは思えません。
タンザニアの助け合いは伝統社会の中にもともとあった相互扶助の規範が都市部で変化を遂げて、現在のような仕組みになったのか、あるいは世界中どこでも自生的に生まれる可能性があるものなのか、どちらなのでしょうか。
小川◉私は「伝統」というよりも、都市的、流動的な現代に対応したものであると思います。タンザニアの人たちは、地域コミュニティーにはあまり重きを置いていません。資本主義経済は自分の労働力を市場で売れば自立して自由に暮らすことができると考える人々に支えられて発展してきた側面があります。不安定な暮らし方をしている彼らも「社会のしがらみ」をどう回避するかに頭を悩ませています。彼らのネットワークは、地縁や血縁による共同体を越えて、不特定多数の人々とつながるインターネット社会に近いものだと私は考えています。
上野◉個人や集団間で、金品やサービスが互いに行き来することを互酬性といいますが、金品を貸し与えても返ってくる保証はなく、賭けやばくちの要素があります。当たり外れはありますが、長い目で見れば帳尻が合い、自分の生存を維持することができます。そのための狡知を「ウジャンジャ」と小川さんは著書の中で紹介していますね。
小川◉タンザニアの人たちは「ウジャンジャ」という言葉を「ずる賢さ」というニュアンスですごく誇らしげに使っています。行商人たちは巧みな話術で顧客を「嘘かもしれないけど、なんだか憎めない。ここはだまされてあげるか」という気持ちにさせながら、商品やサービスを売るのがウジャンジャの真骨頂だと語ります。
ウジャンジャは相手の心を動かす知恵であり、時に相手の経済的、精神的な余裕を見極めながら、ある人からは多くの利益を得たり、別の人には原価割れでも取引をしたりします。そのようなずる賢さによって厳密な互酬性を柔軟に無化できることが大事なのだと思います。
上野◉この交渉力は日本ではコミュニケーション力とも言われます。コンピテンシー(能力)がない人でも、能力がある人を連れてきたり、相手から能力を引き出すことができれば、コミュニケーション力があるといえます。それは子どもや障害を持つ人にも当てはまりますので、その意味では弱さも最強の資源になりますね。
小川◉ウジャンジャには弱さも含まれます。日がな一日、ぼうっとしているおじいちゃんもウジャンジャを持っています。「この人、大丈夫かな」と周囲の人が思わず手助けする。そうした積極的ではない交渉力も現地では「ずる賢さ」と捉えられています。
能力を学習によって身に付けていくという発想とは違い、パソコンの周辺機器のように、周囲の人が働きかけることで自分に能力が付与されていきます。以前、堀江貴文さんの「多動力」という本が話題になりましたが、タンザニアの人たちは「他動力」ですね。
上野◉菅首相の新政権が掲げる「自助、共助、公助」のキャッチフレーズで、自助が最初に来ることにあきれはてました。コロナ禍の今、自助では限界の来た人たちが悲鳴をあげている時に政治家が言うことばとは思えません。
小川◉それはその通りですよね。そのような自助、共助、公助を順番にあるいは連続的に捉えるのが前提としておかしいと思います。確かにタンザニアで自助や共助のしくみが自生的に広がる背景には、社会保障制度が十分に整っていないことが挙げられます。例えば路上で助けてほしいと言われれば、今、私が助けなかったらこの人は死ぬかもしれないと思い、手を差し伸べることもあるでしょうし、政府など頼りにならないとあきらめているからこそ共助も充実します。それが日本にいると、路上で助けてほしいと訴える人については、公助の仕事だという意見をしばしば聞きます。しかし本来は、公助があっても共助が機能し、自助や共助が十全に機能しても公助はより充実するほうがいいですよね。公助と共助があたかもトレードオフの関係のように捉えられることなく、双方ともうまく機能させるにはどうしたらいいのでしょうか。
上野◉日本ではひとり暮らしの高齢者が増え、介護ヘルパーが訪問しないと食事も排せつもままならない人が数多くいます。介護ヘルパーからは高齢者の話し相手になる余裕もないという声をよく耳にします。家族や周囲の人とのコミュニケーションが豊かな高齢者はヘルパーに話し相手を求めないという調査結果もありますから、介護と話し相手は別な人が担えばよい。寝たきりでもオンラインで人と交流できます。公助にしかできないことは公助でしっかりやってもらったうえで、家族や友人は親しい人にしかできないことをやればよいでしょう。
小川◉私の身近にも障害があり、公的な支援を受けている人がいます。公助を受けることで、自分はお荷物になっている、お世話になっていると必要以上に感じてしまい、自己を肯定することが難しくなる場面も見てきたことは、私が贈与や負い目について関心を持ち、自生的に生み出される互助の仕組みを研究対象にするきっかけにもなりました。
上野◉小川さんは、公助が信頼できないからタンザニアで互酬性が発達した、公助が信頼できたら自助と共助は弱体化してしまうと言いましたが、両者は一方を得ると他方を失うというトレードオフの関係でしょうか。公助がないことが家族を追い詰めることもありますから、公助は家族を救います。
公助が信頼できる社会は大事です。あなたの身近で公助を受けている人には、本人や家族が何十年も税金を払ってきたのだから、公助を受けるのは国民の権利だと言ってあげてください。
小川◉私の意見はそれほど上野先生とはずれていないと思います。たしかに私は、公的な保護や保障が得られない世界を研究対象としており、各社会で自発的になされる自助や共助の力を信じていますが、だからといって公助が必要ないとは全く思っていません。実践としてのアナキズムに共感しますが、主義としてのアナキズムは支持していないのです(笑)。公助は公助としてありながら、そして必要な時に当たり前に公助を受けながら、それとは別の次元として誰しもが与えたり受け取ったり返したり、あるいは与えなかったり返さなかったりといった贈与や分配を通じて人と人との個別の関係性の中に生まれる豊かさを味わえる仕組みがあること、あるいは「与える―与えられる」をそれほど意識しないで回していけるような社会ができ、制度やルールよりも総体としての人間社会を信頼できるようになることを願っているのです。
上野◉社会学では人間関係や信頼、ネットワークのことを社会関係資本と呼びます。社会関係資本を構成するのは同質の人たちの集まりよりも、異質の人たちの集まりの方が生存にはより役立つとされています。
私は特定非営利活動法人(NPO)を運営していますが、企業と違ってNPO法人の活動に参加する人たちに地位や報酬を提供することができません。相手の自発性に頼るしか手はありません。長年の活動を通じて人の無理を聞いたり、お返しに無理を聞いてもらったりする信頼関係が、NPO活動の大きな財産になっているのだと、今日の小川さんとの対話であらためて感じました。
小川◉地縁や血縁、会社を基盤とする社縁以外の縁をいかに確保するかが非常に大事で、その縁を結んでいくには持ちつ持たれつの関係をつくっていく必要があります。生涯にわたって自分自身の人生をマネジメントし続けるのは大変なことです。でも、多様な縁があればどこかで誰かが助けてくれます。自分のために投資をすれば自己責任で運用しなければなりませんが、自分以外のものに投資をすれば、その人たちが勝手に運用しているので、うまくいけば運用益が将来、縁とともに戻ってくるかもしれません。
上野◉私はそれを選択縁と呼んでいます。先を見通すことが難しい時代に、危機を乗り越えて生きていくには、人や社会との関係に投資し、貯金しておくといいということですね。
小川◉そのとおりだと思います。今から「縁」を貯金しておかないと、もっと大きな危機がやってくるかもしれませんので。
≪メモ≫
上野千鶴子さんの新型コロナ禍に対する考え方はしばしば催されるオンラインでの講演会のほか、森達也編著『定点観測 新型コロナウイルスと私たちの社会』(論創社)などで触れることができる。同書は「医療」「貧困」「労働」といったテーマごとに17人が論考を寄せており、上野さんは「ジェンダー」を担当。コロナ禍が社会的弱者を直撃する現実を指摘し、今回の対談でも語られたように行政のケアが及ばない部分を、人間関係の力などでしのぐ方法を伝えている。
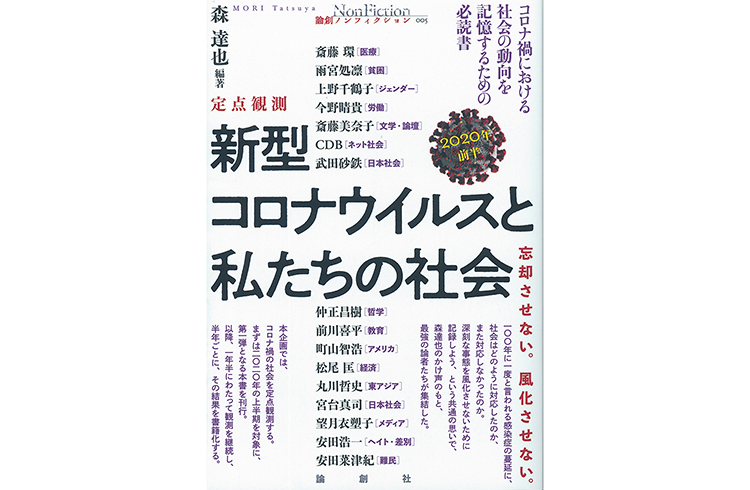
小川さやかさんは、京都新聞「日本人の忘れもの知恵会議」のオンラインフォーラム「ポストコロナを生き抜く知恵」(2020年4月)に登壇。
https://pr.kyoto-np.jp/campaign/nwc_wise/forum/forum_2004.html
このほか対談でも触れられた『思想としての〈新型コロナウイルス禍〉』(河出書房新社)へ寄稿。香港で商売するタンザニア人に密着した『チョンキンマンションのボスは知っている』(春秋社)は、対談に登場するアフリカ経済の一端を紹介している。
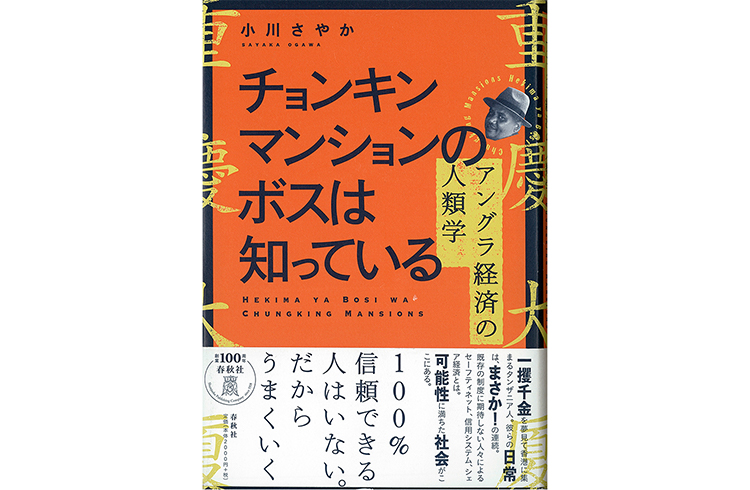
◎小川さやか(おがわ・さやか)
1978年生まれ。立命館大先端総合学術研究科教授。「チョンキンマンションのボスは知っている」(春秋社)で河合隼雄学芸賞、大宅壮一ノンフィクション賞。共著に「思想としての〈新型コロナウイルス禍〉」(河出書房新社)。
◎上野千鶴子(うえの・ちづこ)
1948年生まれ。平安女学院短大、京都精華大などの教壇に立つ。東京大名誉教授。東大では2019年度入学式の祝辞が話題に。著書に「セクシィ・ギャルの大研究」(岩波現代文庫)「おひとりさまの老後」(文春文庫)ほか多数。

