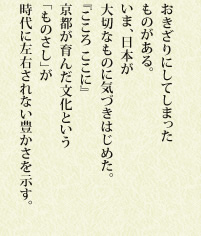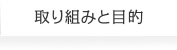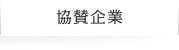- 第22回11月27日掲載
- 自然の音を聞く暮らし
さまざまな命のつながり感じた
多様で豊かな心を取り戻そう

京都大教授
山極 寿一 さん
1952年東京都生まれ。75年京都大学理学部動物学科卒、同大学院理学研究科博士課程修了。京大理学研究科助教授などを経て2002年教授。11年から理学研究科長。著書は「ゴリラとヒトの間」「ゴリラ雑学ノート」など多数。

日本語にはとても擬音語が多い。風がそよそよ、波がじゃぶじゃぶ、木がみしみしと音を立てる。そんな表現を聞くたびに、自然の鼓動が鮮やかに眼前に広がる。私たち日本人は身の回りで奏でられるさまざまな自然の音を言葉としてとらえ、それを再現する能力を磨いてきたのである。
鳥たちがさえずり
虫たちは合唱
闇の奥はにぎわい
私が子どもの頃、日々の暮らしはそんな音に満ちていた。朝はまだ暗いうちから鳥たちがさえずりはじめたし、夏の夜は虫たちの合唱で闇の奥はいつもにぎわっていた。朝起きて蚊帳を外すと、色とりどりのコガネムシや蛾(が)が畳の上を這(は)いまわっていた。近くの雑木林に行けば、いやというほどクワガタムシやカブトムシが捕れた。
ところが最近はすっかり虫の声を聞かなくなった。暑い夜に窓を開け放していても全く虫が入ってこない。鳥の声もカエルの声もほとんど聞こえなくなった。それぞれの家が冷房をかけるので、街には熱風が充満し、とても窓を開けてはいられない。したがって聞こえるのは人工的な音かテレビから流れてくる音だけになる。いったいいつからこんなことになったのだろう。
山、里山、里は精神的な世界を分ける基準だった

日本は世界でも有数の生物多様性の高い国である。それは熱帯に負けないほどの雨量と、日本列島の海岸を洗う暖流によって豊かな森があることが原因である。加えて、日本列島を南北に走る脊梁(せきりょう)山脈によって農耕に適しない険しい地形が森を残した。さらに、肉食を禁ずる宗教や牧畜を発達させなかった文化が、野生動物たちが生き残る環境を作った。奥山、里山、里という呼び方は、野生動物と人の暮らしを分ける空間的区分であると同時に、人々の精神的な世界を分ける基準でもあった。奥山はめったに人が足を踏み入れない神聖な場所、里は野生動物の侵入を許さない人間の居住地だった。そして、里山は人間が里で暮らすための材料を採集し、野生動物と出くわす場所だったのである。薪炭林として常に人が手を入れていた里山の二次林は虫たちの宝庫でもあり、幾種類もの鳥たちが虫や果実を食べにやってくる楽園でもあった。戦後にその生物たちのバランスが急速に崩れてしまったのである。
その原因は、大規模な造林事業と道路建設、農業の改変にある。成長の遅い広葉樹を伐採してスギやヒノキを植林し、山岳地形を切り崩して都市間をつなぐスーパー林道を開設した結果、奥山は野生動物たちが住む場所ではなくなった。エネルギー革命と農業の機械化、それに換金作物の栽培が奨励されたおかげで、農業人口が急減して里山や畑が放棄されるようになった。奥山を追われたシカやクマやサルたちが人里近く現れて悪さをするようになったのだ。
自然からの隔離で単純な便利さ手に入れて

害を働く動物たちに敵意の目を向けるようになった人々は、自分たちの暮らしをますます自然から隔離するようになった。自然の音が遠ざかったのはその結果である。でもそれは私たちの心をも自然から遠ざけ、自分とは違う生き物の鼓動に耳を傾ける姿勢を忘れさせた。単純で便利な世界を手に入れたおかげで、私たちは多様で豊かな心を失った。さまざまな命のつながりが感じられた夜を懐かしく思う。
<日本の暦>
鳥と七十二候
1年の気候変化を72に区分した七十二候で、もっともよく登場する動物は鳥です。明治時代の略本暦でも「玄鳥去(つばめさる)」「鴻雁来(こうがんきたる)」など9候にのぼります。
京都の現代版七十二候を作るとすれば、初冬期に外せないのが鴨川のユリカモメ。ことしもカムチャツカ半島からはるばる飛来、にぎやかさと愛くるしさは例年通りです。
古代、中世に多くの和歌に詠まれた都鳥(みやこどり)は実はユリカモメであるという説が有力です。「都鳥鳴(みやこどりなく)」。この時期の京都七十二候に、まさにぴったりです。
<リレーメッセージ>

■おさきーです
「おさきーです」。その一言でふっとあたたかな気持ちになれる、私が大好きな京都弁ですが、実際に耳にすることや、私自身も口にすることが少なくなったと感じる今日この頃です。
3月11日の東日本大震災の日、演奏旅行で山形市にいました。停電や断水など混乱の中、現地に二日間待機しましたが、関西での公演があり至急戻らないといけなかった私は、とにかく動き始めた高速バスに乗り、新潟経由で京都へ向かおうと決めました。
ダウンコートを着込み夜明け前からロータリーの大行列に並び、整理券の配布をただひたすら待ちました。行列の見知らぬ方々と、白い息を吐きながら、声を掛け合いながら過ごしました。そしてやっとのことでバスに乗車できてひと安心した時、近くの席の年配の男性がドーナツを差し出して下さいました。「どうぞどうぞ」「あなたからどうぞ」「あなたこそどうぞ」。周囲の数人で順に分け合って口にしました。
やり取りは京都弁ではなかったけれど、極限の状況にありながらも人を思いやる「おさきーです」の気持ちがたくさん詰まった、ひとかけらのドーナツの味でした。
(次回のリレーメッセージは、京都芸術祭音楽部門「びわ湖国際フルートコンクール」実行委員長の白石孝子さんです)