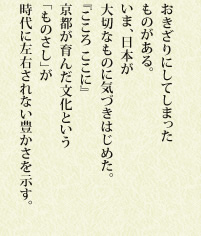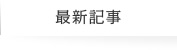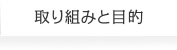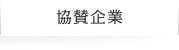バックナンバー > 第10回 工夫してみる
- 第10回9月4日掲載
- 工夫してみる
依頼に慣れ切った己を戒め
手の届くものでやりくりを

裏千家家元
千宗室 さん
1956年、京都市生まれ。同志社大卒。中村祖順大徳寺管長の下で得度、坐忘斎の号を受ける。祖順老師没後、盛永宗興老師に参禅。2002年12月、千宗室家元を継承。著書に「ほおづえついて」「母の居た場所」など。

今年(2011年)の梅雨明けは早かった。投げやりな雨の日が続くと思っていたら、突然猛暑になった。それも日差しが違う。
遠慮のない夏の始まり
怒濤の勢いで
例年だと夏の始まりには遠慮がある。どのぐらい照ったらよいのだろうかとの躊躇(ちゅうちょ)がお日様に感じられる。それまで雨雲のカーテンの向こうでぬくぬくしていたところを、突然人目に曝(さら)されてしまった戸惑いがある。うぶなのだ。だから梅雨前線に取り残されてしまった要領の悪い湿った空気の残党を炙(あぶ)って追いやることができない。てかりだした椿(つばき)の葉の上でそれが一息吐(つ)いているのを見てみぬ振りする気の好(よ)さがある。
それが今年はどうだったろう。貴船の水まつりが終わった途端、挨拶(あいさつ)なしで真夏になった。陽光は叩(たた)きつけるように降り注ぐ。正(まさ)に怒涛(どとう)の勢いである。
節電は誰もが心がけていた。出来るだけ辛抱した。我が家などあまりエアコンとのお付き合いがない方と思うが、それでもいつも以上に注意した。
茶の湯では季節を遮断しない。どのように手強(ごわ)い一日を迎えても、それと折り合いをつける道を探す。確かに猛暑だとそこから離れたくなる。しかし、茶室にはエアコンはない。扇風機もない。涼しくするのは難しい。但(ただ)し、涼しく感じあう工夫がある。その工夫することが暑さとの折り合いをつける手立てなのだ。
細い水指の蓋代わりに葉を用い水滴打つ

たとえば七月や八月だと、細い水指(みずさし)の蓋(ふた)代わりに梶の葉や蓮の葉などを用いる点前がある。葉の上には水滴を打つ。よく見ると席中に入り込む昼の日差しが水滴に閉じ込められ、ぷるぷる震えている。一瞬、暑さが遠のく。
工夫、と記してきたが、それは茶の湯の世界だけのものではない。誰でも出来るし、どこにでもある。面倒くさがらなければ、だが。
スイカを思い浮かべていただきたい。夏の日に付き物のお八(や)つだった。それがいつの間にか主役の座から下り、アイスクリームなどに取って代わられた。確かにお菓子類だと買うのは簡単で、始末も手軽だ。スイカはそうはいかない。冷やして切り分けなくては口に入らない。切り分けてあればそれでよいかというとそうでもない。スーパーなどで切り売りしてあるものからは既に涼味が失(う)せている。
手間はかかるがそれだけの価値がある

冷やした丸ごとのスイカを目の前に置く。なんとなく頭を叩き、それから包丁の刃を差し込む。途中までいったらそこで割るように分ける。そのときパカッと音が立つ。そうして中から冷気が逃げてくる。それが顔をかすめるとき、瞬く間だが夏の昼下がりから刺(とげ)々しさが消える。冷やし、切り分ける、という手間はかかるが、それだけの価値がある。
何でも手に入る世の中になった。だから私たちは贅沢(ぜいたく)になり我儘(わがまま)になった。心も体も動かさず、依頼ばかりするのに慣れきった己を戒め、たまには手の届くものでやりくりしてみては如何(いかが)だろう。工夫することによって得られる満足感は、流通に乗って手元に届けられるものとは一味違う。そう私は思っている。
<日本の暦>
白露 (9月8日ごろ)
空の色、風の音にも秋の気配が漂い、野の草、庭の花にしらつゆが光る候。ススキの穂が伸び、ハギやキキョウが咲いて、庭の虫たちもすだき始めます。
「夕月夜 心もしのに白露の 置くこの庭に こほろぎ鳴くも」。万葉集第8巻、湯原王の一首は、もの悲しいこの時候の風情を見事にうたっています。万葉時代の「こほろぎ」は、スズムシ、マツムシを含め秋の虫の総称でした。湯原王の心を動かしたのは、どの虫だったのでしょう。
<リレーメッセージ>

■知恵と工夫のDNA
平安時代から都市であり続けた京都には、何度も危機があったはず。しかしその都度、知恵と工夫で不死鳥のように甦(よみがえ)り歴史を刻んできた。近いところでは明治時代、疏水事業に代表される近代的都市基盤整備を行い、積極的に外国の技術を導入した開明的な企業人の努力などによって、東京遷都の大打撃を乗り切った。また、戦後の復興期には、伝統技術を先端技術に昇華させたベンチャー企業が次々に生まれ、「京都銘柄」の上場が相次ぎ、京都発の世界企業が誕生していった。歴史は革新あってこそであり、京都の濃密で重層的な都市の力がそれを支えてきた。
今日に至るまで、新しい技術やビジネスモデルの創出は京都の強みとなり、独自性の強い企業が数多く存在している。京都の企業は、海外での圧倒的なブランド力や都市そのものの魅力によって、容易に本社を移したりはしない。京都の文化や芸術が変らず命脈を保てるのも、地元企業の力によるところが大きい。
その京都も近年、事業所数や生産年齢人口の減少が続いている。混沌(こんとん)としたこの時代にこそ、知恵と工夫のDNAを呼び覚ますことが大切だ。
(次回のメッセージは、歌人の永田紅さんです)