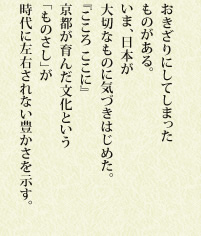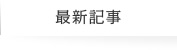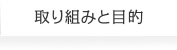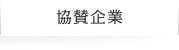バックナンバー > 第6回 いけばなの心
- 第6回8月7日掲載
- いけばなの心
明日には枯れていく花が より強く生を感じさせる

華道家元池坊 次期家元
池坊 由紀 さん
華道家元次期四十六世として、国内外でのいけばな振興はもとより、講演や大学での講義など、いのちを生かすといういけばなの精神に基づいた活動を行なっている。財団法人日本いけばな芸術協会副会長。

88才の先生が、京都の本部に研修に来ている。弟子も沢山いながらもっと上手くなりたいと言う。異なる世代のクラスメートに混じりながら、しっかりノートを取り勉強する。
かと思えば、原爆で亡くなった母親がいつも花をいけていたその姿が懐かしくて、いけばなを始めた女性もいる。娘のお稽古の送迎をしているうちに、一緒に始めた父親もいる。様々な事情で残念ながら途中でやめたり、亡くなられた方もいる。
ひとりひとりが
生きる厳しさ喜び
見せてくれる
いけばなをしていてよかったことは、季節に敏感になったり、花をうまくいける技術が身についたことだけでなくむしろ、そういった人達を幼い頃から間近に、たくさん見てきたことかもしれないと思う。
年齢も出身も家庭環境も異なるひとりひとりが、そしてそのだれもが明るく軽やかにふるまいながらも、人が生きる厳しさと喜びをまざまざと見せてくれていたからだ。
喜びの姿、悲しみの姿、苦しみの姿、そのどれもが生きている証であり、私に人が生きることはどういうことなのか、ふみ出す強さと共に耐えることにも強さがいることを教えてくれた。
花は花であって、花だけにとどまらない不思議な存在である。
ある人にとっては花は母である。歳月とともに薄れゆく母の記憶が、花をいける度にそこに踏みとどまる。時空を超えて同じことをしている母と娘になる。
またある人にとっては、自分が生きてきた軌跡であり、今日も生きているという、そして明日も生きていこうとする実感なのだろう。
明日には枯れていく花が、有限性を持つが故に、より強く生を意識させる。そして人と人の時と心を結んでいく。
これまで出会った人達は、その誰もがまさに目には見えない、けれども確かな絆と心の体現者だったと思う。
さりげない営み 人生と重なり響き合う

伝統文化とは、きっとそういうものなのだろう。かたくるしいことや改まったことを特別にするのではなく、これは芸術だと声高に主張するのでもなく、花をいけたり茶をたてたりする日々のさりげない営みなのだ。どこにでもありそうな平凡な、けれども本当はどの貌(かお)も違っているかけがえないその人だけの暮らしの中で、その人の思いや人生と重なり、それが他者とも響き合い伝わってきたものなのだろう。
そしてそれは極めて個人的なものなのだが、つきつめると人としての普遍性にも突き当たっていく。
何かを思い、誰かを思い、花をコップにさせばそれは立派ないけばなになる。そうして受け継がれ手渡されていくのが伝統になる。
1462年、東福寺の禅僧 雲泉太極が書き記した『碧山日録』の2月25日条には、池坊専慶が、金瓶に草花数十枝を挿したところ、洛中の好事家が競ってこれを鑑賞したことが記されている。その時から来年で550年を迎える。
いけばなの起源とされる仏前供花の時代から考えると、その歴史は更にさかのぼる。残らなかったこととなかったことは違う。
形に残らないものだからこそ今一度意味を考えたい

いけばなという形の残らないものがなぜ続いてきたのだろう、枯れてしまうものに、消えてゆくものに人が見てきたのは形を超えた何かではなかったのか。そして私たちは何を次代に伝えようとしているのだろう。形に残らないもの、消えてゆくものだからこそ持つ意味をもう一度考えたい。
<日本の暦>
立秋 (8月8日)
この日から秋という節気。暦のうえでは立秋から立冬の前日までを秋と呼びます。しかし現実には、まだまだ暑い時候です。
とはいえ、早朝や夕方には風のそよぎや雲の様子にふと秋を感じるころ。夏から秋への移ろいを肌で感じられる季節でもあります。
先人たちはこのころを秋の始まりととらえていました。涼風がたち、庭では虫たちがすだき始め、「秋来ぬと 目にはさやかに見えねども 風の音にぞ おどろかれぬる」と藤原敏行が詠み、正岡子規が「秋雲は砂のごとく」としたためたような季節感だったのです。
<リレーメッセージ>

■遅れついでに
京都は一周遅れのトップランナーだという面白い比喩がある。
陸上競技で一周分遅れているランナーがあたかもトップを走っているように見えるアレである。近代化に後れを取ったにも係らず、時代の流れが物の基準値を変えていき、先進的な都市より、古き良き物を守る京都が評価のトップに立っているとの事らしい。
確かに京都は伝統文化やその特殊な生活風習には誇りを持ち、したたかに守り継承してきているが、町の景観となると―如何(いかが)なものか。
西陣で生まれ育った私は今もこの地で古い町家を再生し仕事の拠点をしいているが、周囲の残すべき家屋は相変わらず無情ともいえる早さで取り壊され、マスコミ等の情報をたよりに整然と並んだ古い町家を期待し訪れる観光客をがっかりさせている。
私はつくづく思う。京都は飽食ならぬ飽財の町。“ほんまもん”の“お宝”がぎょうさんすぎて、その価値が見失われている。
私はつくづく思う。一周遅れのランナーなら遅れついでに常に後を振り返り、大切な落し物をしていないか確認しながら走って頂けないかしらと。私はそんな京都の応援がしたい。
(次回のメッセージは人形作家の森小夜子さんです)